ネットショップを開業したいけれど、何から始めればよいか分からない——そんな不安を抱える方は少なくありません。商品選びやサイトの作成、必要な手続き、集客の方法まで、始めてみると意外とやることは多くあります。この記事では、個人でも無理なく始められるネットショップ開業の具体的なステップや注意点を解説していきます。
ネットショップの開業を考える前に知っておきたいこと

ネットショップを始めたいと考える人の多くが、「自宅で気軽にできそう」「副業にぴったりかも」と期待を抱いています。しかし、現実には準備すべきことや乗り越えるべき課題も多く存在します。ネットショップ開業に向いている人の特徴や、よくある失敗のパターンをもとに、開業前に知っておくべき基礎知識をお伝えします。
個人でもできる?開業の現実と向いている人
ネットショップは、法人でなくても個人で開業可能です。たとえば、主婦の方がハンドメイド雑貨を販売したり、会社員が副業としてアパレルを扱ったりと、実際に多くの個人が開業しています。しかし、個人で始められるからといって、誰にでも成功するわけではありません。
成功している人の共通点には、以下のような特徴が見られます。
- 小さくても明確なコンセプトを持っている
- 継続的に学ぶ意欲がある
- 地道な作業や改善をいとわない
- 顧客目線で考えられる
向いているか不安な方は、まず自分の「売りたいもの」と「誰に届けたいか」を紙に書き出してみましょう。それだけでも、開業後の方向性が明確になっていきます。
よくある失敗例から学ぶ「始め方の落とし穴」
ネットショップ開業でつまずく人の多くが、次のような落とし穴にはまっています。
- 「売れるだろう」と思って仕入れすぎて在庫を抱える
- 集客やSEOの知識がなく、開業してもアクセスがゼロ
- ショップのデザインや文章が信頼感に欠け、購入されない
- リサーチ不足で競合が多すぎるジャンルに参入
ネットショップを始めたものの、数か月たっても注文がまったく入らないというケースも珍しくありません。たとえば、商品写真が暗かったり、説明文が不十分だったりすると、購入をためらわれてしまうことがあります。信頼感の欠如は、売上に直結します。開業初期こそ、見せ方や伝え方をしっかり整えることが大切です。
このような失敗は、事前に情報を集め、準備を怠らなければ防げます。とくに「売れる仕組み」を理解してからスタートすることが、失敗を避ける最大のポイントです。
何を売る?ネットショップの商品選びの考え方

ネットショップの成否を大きく左右するのが、「何を売るか」という選択です。どんなにおしゃれなサイトを作っても、商品に魅力がなければ売れません。ここでは、オリジナル商品と仕入れ商品の違い、そして売れやすいジャンルと避けたほうがよいジャンルについて詳しく解説します。
自分の商品を作るか、仕入れるかの選択
ネットショップで扱う商品は、大きく分けて「自分で作る」か「他社から仕入れる」かの二択になります。それぞれにメリットとデメリットがあります。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自作商品 | 差別化しやすい/ファンがつきやすい | 製作に時間と手間がかかる |
| 仕入れ商品 | 初期投入が少なく始めやすい | 他店との競争が激しく、価格競争になりやすい |
たとえば、オリジナル性の高いハンドメイド商品は、色合いやデザインの工夫が伝わればSNSなどで注目されやすく、ファンがつく可能性もあります。一方で、仕入れ商品の場合は他店と扱う商品が重複しやすく、価格競争に巻き込まれて思うように利益が出ないこともあります。どちらを選ぶにしても、販売方法との相性を意識することが重要です。
売れやすいジャンルと避けたいジャンル
ネットショップには、「初心者でも売れやすい」と言われるジャンルがあります。逆に、難易度の高いジャンルも存在します。下記は一例です。
売れやすいジャンル
- ハンドメイド雑貨(個性が出せてファンがつきやすい)
- スキンケア・コスメ(リピート率が高い)
- ペット用品(ニッチで熱心なファンが多い)
避けたほうがよいジャンル(初心者向けではない)
- 家電・PC関連(競合が大手・返品対応が複雑)
- 食品全般(許可や保存管理が必要)
- ブランド品(真贋トラブルが発生しやすい)
たとえば、中古家電のように初期不良や動作確認が必要な商品は、クレームや返品対応に手間がかかり、初心者には負担が大きくなりがちです。反対に、スキンケア商品のようにリピートが見込める商材であれば、広告費を抑えても安定した売上につながることがあります。商品ジャンルによって運営の難易度や収益構造が大きく異なる点には注意が必要です。
迷ったときは、自分が「自分がくり返し買いたくなるもの」や「強くおすすめできるもの」を選ぶのがおすすめです。売れるかどうかは、商品そのものだけでなく、売り手の“思い”と“見せ方”にも左右されます。
ネット販売の始め方|個人事業主になる準備


ネットショップを本格的に運営するなら、ビジネスとしての基盤づくりが欠かせません。とくに個人で始める場合、開業届の提出や青色申告などの税務準備、さらに商品によっては販売許可が必要になります。
開業届・屋号・青色申告のポイント
ネット販売を始める多くの人が、まず「開業届って本当に必要?」と疑問を抱きます。結論から言えば、利益が出る前でも、ビジネスとして行うなら提出しておいたほうがメリットは大きいです。
開業届は、税務署に提出する書類で、個人事業主としてのスタートを公式に届け出るものです。あわせて、任意で「屋号」を登録することもできます。たとえば、屋号を登録しておくことで、銀行口座や請求書にショップ名を使えるようになり、名義に統一感が出ます。これによって、取引先やお客様からの信頼感が高まることもあります。
そしてもうひとつ重要なのが「青色申告承認申請書」の提出です。青色申告には以下のようなメリットがあります。
- 最大65万円の所得控除
- 赤字の繰越が最大3年可能
- 家族への給与を経費計上できる(専従者給与)
ただし、帳簿付けや仕訳が必要になるため、クラウド会計ソフトの導入や税理士への相談も視野に入れておくと安心です。とくに副業から始める人は、「開業届+青色申告セット」でスタートすることが、あとから大きな節税効果につながります。
販売に必要な許可と注意点(食品・化粧品など)
ネットショップでは、販売する商品によって行政の許可が必要になる場合があります。以下は、代表的なジャンルと必要な許認可です。
| 商品ジャンル | 必要な許可・資格 | 管轄機関 |
|---|---|---|
| 食品 | 食品衛生責任者+営業許可 | 保健所 |
| 化粧品 | 化粧品製造販売業許可 | 都道府県の薬務課 |
| 中古品 | 古物商許可 | 警察署(公安委員会) |
| 医薬部外品 | 製造販売業+販売許可 | 都道府県の薬務課 |
また、許可の有無だけでなく、商品ページへの表現にも注意が必要です。とくに化粧品やサプリメントでは、「効能を保証するような記載」は薬機法違反になるおそれがあります。
これから商品を扱う方は、まず「その商品には許可が必要か」「どうすれば取得できるか」をリストアップし、自治体や行政サイトで確認しておきましょう。法令を守る姿勢は、ショップの信頼感を高め、トラブル防止にもつながります。
仕入れの基本とおすすめルート


ネットショップで販売する商品を仕入れる際、「どこから・どのように仕入れるか」は売上と利益に直結します。特に初心者は、在庫リスクを最小限にしつつ、信頼できる仕入れ先を見つけることが重要です。小ロット仕入れの始め方と、海外調達やドロップシッピングの可能性について詳しく解説します。
小ロットから始める仕入れ先の選び方
ネットショップ初心者にとって、大量仕入れはリスクが高く、在庫過多による赤字に直結することもあります。そのため、まずは「小ロットでテスト販売」から始めるのが賢明です。
具体的な仕入れ先の例としては以下のようなものがあります。
| 種別 | 特徴 |
|---|---|
| 国内卸サイト | 最低注文数が少なく、納期が早い(例:NETSEA、スーパーデリバリー) |
| 地域の問屋・展示会 | 実際に商品を手に取れる/交渉次第で小ロット対応可 |
| メーカー直取引 | 商品知識や差別化が可能/信頼関係の構築が重要 |
まずは少量で販売感触を確認し、徐々に信頼できるパートナーを増やしていくことが、リスクを抑えた仕入れの第一歩です。
小ロットで仕入れる際は、価格よりも「継続的に供給できるか」「商品の質にばらつきがないか」といった点に注目しましょう。
海外仕入れ・ドロップシッピングという選択肢
国内だけでなく、海外にも優良な仕入れ先は数多く存在します。特に注目されているのが、中国やアメリカなどからの直輸入、そして在庫を持たずに販売できる「ドロップシッピング」という方法です。
【海外仕入れの特徴】
- Alibaba、1688.comなどで低価格大量調達が可能
- 為替や関税、輸送費に注意
- 輸入許可や検品体制の確認が必要
【ドロップシッピングの特徴】
- 在庫不要で販売リスクが小さい
- 商品発送は提携先が行うため作業負担が少ない
- 差別化が難しく、同じ商品を扱う店舗が多い傾向
たとえば、海外サイトから商品を輸入する場合は、仕入れコストを抑えられる一方で、検品やトラブル対応の負担が発生することがあります。逆に、ドロップシッピングを活用すれば在庫管理の手間がなく、オリジナル商品で自分のブランドを広げやすいというメリットもあります。
海外仕入れやドロップシッピングは、初期費用を抑えて始めたい方にとって有力な選択肢です。ただし、安定供給や品質管理に課題もあるため、小さく試して実績を積みながらスケールする戦略が重要です。
まずは1商品から、テスト的に導入してみるのがよいでしょう。
自分に合ったネットショップ作成サービスを選ぶ


ネットショップを始める際、どのサービスを使うかによって、売上・運営効率・成長スピードは大きく変わります。初心者にとっては操作性がわかりやすく、かつ成長にあわせて拡張できるサービスを選ぶことが大切です。ここでは、人気のサービス3社の特徴と、初心者におすすめの選び方を紹介します。
BASE・STORES・Shopifyなどの違いと特徴
現在、国内で多くの個人が利用しているのが「BASE」「STORES」「Shopify」です。それぞれに強みと向いているユーザー像があり、目的によって選ぶべきサービスは異なります。
| サービス名 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| BASE | 初期費用・月額無料。テンプレートが豊富で、操作が簡単。 | できるだけコストをかけずに気軽に始めたい人 |
| STORES | 無料プランでも十分使え、クーポン機能など販売促進機能が強い。 | 小規模でも本格的な販売を目指す人 |
| Shopify | 海外でも通用する機能と自由度。決済や拡張機能も多彩。 | 将来的にブランド化や越境ECを目指す人 |
たとえば、BASEのようなサービスを使えば、SNSと連携して手軽にネットショップを始め、少しずつ売上を伸ばすことも可能です。一方で、Shopifyのように機能が豊富なサービスを選べば、海外展開やブランドの成長につなげやすい場合もあります。
デザイン性・機能・コストのバランスを見ながら、自分のスタート地点に合ったものを選びましょう。
初心者向けおすすめランキングと選び方
ネットショップ初心者が選ぶべきサービスは、「使いやすさ」「初期費用の低さ」「サポートの充実度」がポイントになります。以下は、専門家視点で評価した初心者向けのランキングです。
初心者向けおすすめランキング(2025年版)
1位:BASE(コストゼロで始めやすく、管理画面も直感的)
2位:STORES(無料でも機能が充実し、集客支援も手厚い)
3位:カラーミーショップ(デザイン自由度が高く、独自ドメインに強い)
4位:Shopify(やや上級者向けだが、拡張性と信頼性は抜群)
選ぶ際は、次の視点で比較してみましょう。
- 初期費用・月額費用の有無
- 商品点数とカテゴリの上限
- 集客支援や販促機能の有無
- デザインの自由度とテンプレート数
- 決済手段とその手数料
実際にいくつかのサービスに登録し、管理画面の使いやすさやショップの見え方をテストしてみるのもおすすめです。サービス選びは、「どれが有名か」ではなく、「自分の事業に合っているか」で判断することが重要です。
開業後に失敗しないための運営・集客の基本


ネットショップは開設して終わりではありません。開業後こそが本番であり、運営と集客の質が、売上の伸びを左右します。継続的なアクセスと信頼を得るには、サイト全体の印象づくりと、お客様との接点を意識した施策が欠かせません。
お店の信頼感を高める方法(デザイン・レビュー)
ネットショップは対面販売と違い、店舗やスタッフの顔が見えません。そのため「このお店で買って大丈夫?」という不安を取り除く工夫が重要です。信頼感を生む要素には、デザインとレビューの2つがあります。
まず、ショップのデザインは第一印象を大きく左右します。商品写真のクオリティ、文字の読みやすさ、配色の統一感が整っていないと、購入をためらわれてしまいます。たとえば、サイトの配色を統一したり、商品画像を白背景でそろえることで、ショップ全体の印象が整い、購入につながりやすくなることがあります。
次に、レビューの存在です。お客様の声があるだけで、「自分も安心して買えそう」という気持ちになります。レビューを集めるコツとしては、以下のような方法があります。
- 購入後に自動でレビュー依頼メールを送る
- レビュー投稿者にクーポンを提供する
- SNSでの投稿を許可を得て掲載する
とくにスタート直後は、知人やモニターに商品を提供し、正直な感想をもらうことで、レビュー欄を充実させるのもひとつの手です。見た目と声の両面から、「信頼できるお店」という印象を築いていきましょう。
集客の基本(SEO・SNS・広告)と続ける工夫
どれだけ良い商品でも、存在を知られなければ売れません。集客は「見つけてもらう工夫」の積み重ねです。代表的な集客手段は、SEO(検索対策)、SNS、そして広告の3つです。
【SEO対策の基本】
- 商品名や説明文に検索されやすいキーワードを入れる
- タイトルや画像にaltタグを設定する
- ブログやコラムで関連情報を発信する
【SNS活用のポイント】
- インスタグラムはビジュアルで惹きつけるのに最適
- X(旧Twitter)は日常投稿でファンとの距離を縮める
- 投稿には一貫した世界観とハッシュタグを使う
【広告を使うタイミング】
- まずは少額からInstagram広告やGoogle広告でテスト
- 反応が良かった投稿や商品にだけ出稿を集中させる
集客は「短期で成果を出す施策」と「長期的に信頼を築く施策」のバランスが大切です。いきなり完璧を目指さず、ひとつずつ試しながら改善を重ねていくことが、結果につながります。まずは、自分にとって無理なく続けられる集客法を一つ決めて、毎日コツコツと実行してみましょう。


最初の売上をつくるためにやるべきこと


ネットショップ開業後、最初の売上を得られるかどうかは、その後のモチベーションにも大きく影響します。しかし、開店直後に自然と商品が売れるケースはごくわずかです。最初の1ヶ月でどのような行動を取るか、そしてリピーターを生む運営習慣をどう作るかが、継続的な成果につながります。
はじめの1ヶ月で意識したいポイント
「最初の1件をどう作るか」は、多くのネットショップ初心者が直面する壁です。開業後1ヶ月間は、“売る”より“見つけてもらう”ことに集中しましょう。具体的には以下のポイントが重要です。
- SNSでショップ開設を発信(顔出しや想いを添えると効果的)
- 知人・友人に案内し、初期レビューをもらう
- 期間限定のクーポンや送料無料キャンペーンを実施
- 商品数は少なくても、説明文と写真を丁寧に仕上げる
開業直後にインスタライブやSNSで商品を紹介し、クーポンなどの特典を活用すれば、その場で注文が入ったり、レビューを得られる可能性もあります。
購入のきっかけになるのは、ショップに「人らしさ」や「温度感」を感じられる工夫です。
また、データをもとに改善する姿勢も欠かせません。Googleアナリティクスやショップ管理画面を活用し、「どのページが見られているか」「どこで離脱されているか」を毎週チェックしておくと、具体的な改善点が見えてきます。売れなくても、あきらめずに工夫を重ねていくことが大切です。
リピーターにつながる運営の習慣化
一度買ってくれたお客様を「もう一度買いたい」と思わせるには、商品そのものの質だけでなく、体験全体の満足度が重要です。初回購入者をリピーターに育てるには、以下のような習慣を意識しましょう。
- 配送時に一言メッセージや試供品を同封
- 購入後3日〜1週間以内にフォローメールを送る
- 購入月から1ヶ月後に再来店を促すクーポンを配信
- SNSで購入者にお礼を伝える(許可を得たうえで)
たとえば、購入時に直筆メッセージや次回使えるクーポンを同封することで、リピート率が上がることもあります。大手にはない「人のぬくもり」を伝えられるのは、個人ショップならではの強みです。
また、レビューをもとに商品改善を重ねることで、購入者の満足度はさらに高まります。定期的にお客様の声を読み返し、ショップ運営に反映させていきましょう。
売上は“数”より“信頼”で伸ばしていくものです。ひとりのお客様を大切にし、その関係性を深めることが、次の売上を自然に呼び込む道になります。最初の1ヶ月は、売る努力よりも“信頼を積み重ねる”習慣づくりから始めましょう。
よくある質問
- ネットショップを運営する月収はいくらですか?
-
ネットショップの月収は、取り扱う商品ジャンルや集客力、販売戦略によって大きく差があります。副業レベルでは月1〜5万円程度の人もいれば、本業として取り組み月30万円以上稼ぐ人もいます。ただし、初期はほとんど利益が出ない期間も想定し、継続的な改善が重要です。
- ネットショップを開業するには何をすればいいですか?
-
ネットショップ開業には、販売する商品の選定、開業届の提出、ショップ構築サービスの登録、商品撮影と説明文の作成、決済設定、集客準備が必要です。食品や化粧品など一部の商品には許可や資格も必要です。無理なく始められる範囲で、段階的に進めるのがポイントです。
- ネットショップの廃業率は?
-
一般的にネットショップの廃業率は1年以内で約30〜40%、3年以内では半数を超えるとも言われています。原因は、利益が出ない、継続的な集客ができない、在庫管理の失敗など。継続には、無理のない運営体制と、初期段階での十分な準備と改善意識が欠かせません。
- 一番売れるECサイトは?
-
日本国内で最も売上規模が大きいECサイトはAmazonです。次いで楽天市場、Yahoo!ショッピングが続きます。Amazonは物流と集客に強く、売上が伸びやすい傾向にありますが、手数料も高めです。売れやすさだけでなく、自分の商品に合う販路を選ぶことが大切です。
- ネットショップのオーナーの収入はいくらくらいですか?
-
ネットショップのオーナー収入は、月数万円の副業から月100万円を超える専業まで幅広いです。特に在庫を持つ自社EC型と、在庫を持たないドロップシッピング型では利益率に差が出ます。初期は収入が不安定でも、仕組みを整えることで安定収益につながる可能性があります。
- ネットショップサイトの売上ランキングは?
-
2024年のデータによると、日本国内のEC売上ランキングは1位Amazon、2位楽天市場、3位Yahoo!ショッピングとなっています。海外を含めるとAlibabaやShopeeなども急成長中です。売上規模は重要ですが、競合の多さや手数料も考慮して販路を選びましょう。
ネットショップ開業は、正しい準備と運営方法を知っていれば誰でも可能です。完璧なスタートでなくても、自分のペースで進めることが何より大切です。この記事を参考に、あなたらしいお店づくりの一歩を踏み出してみてください。コツコツと続けていくことで、きっと理想のかたちに近づいていきます。



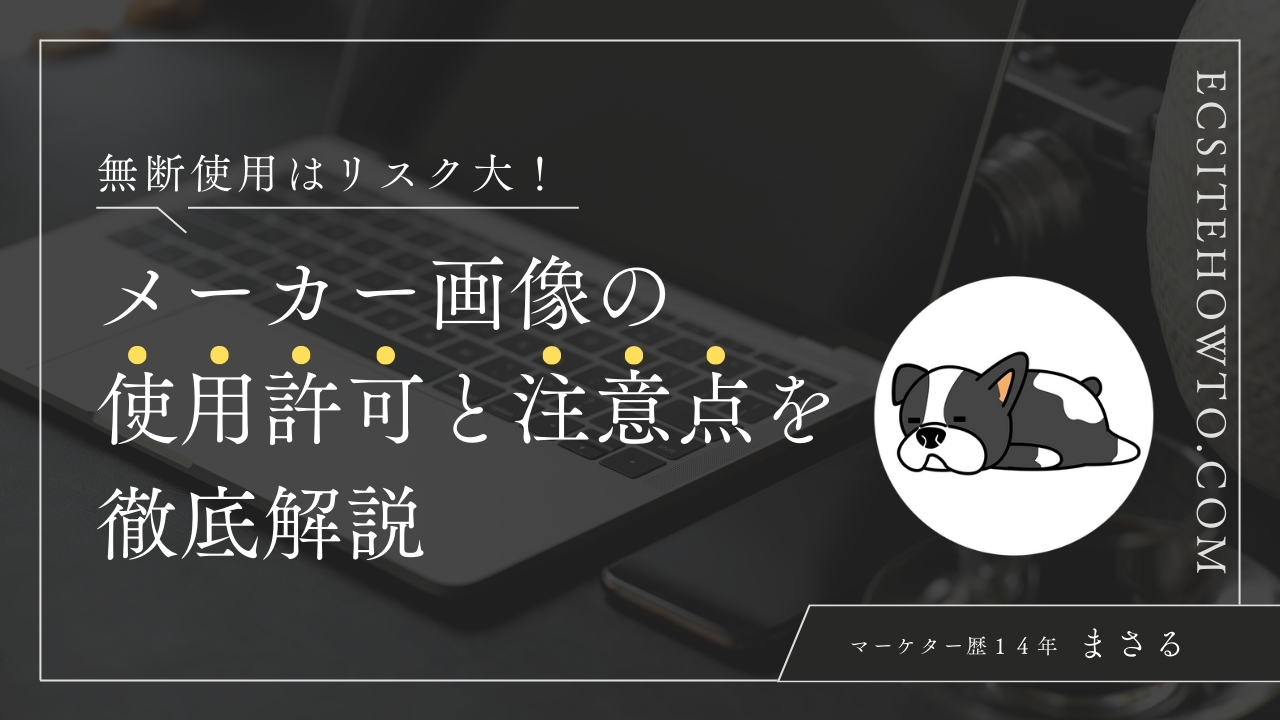

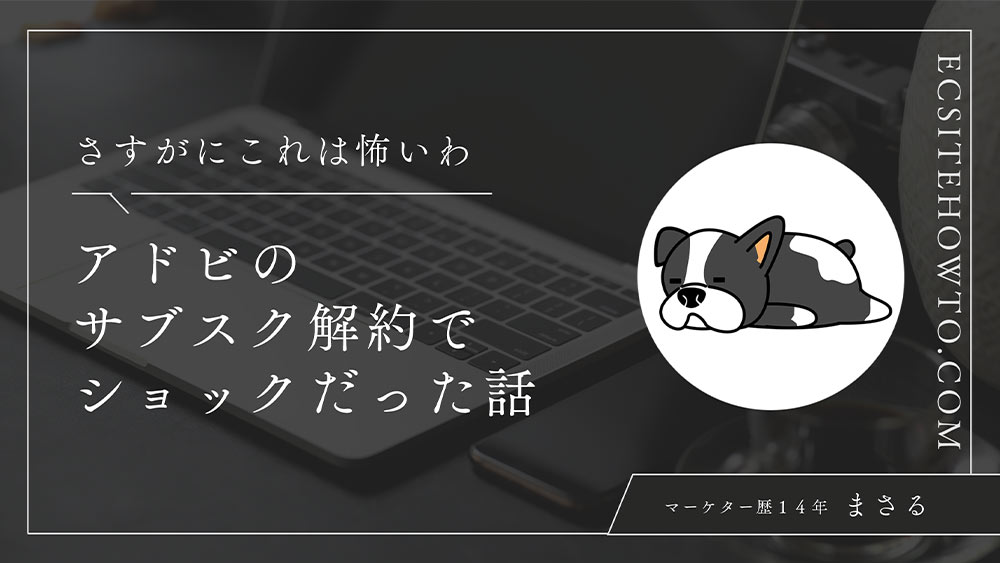
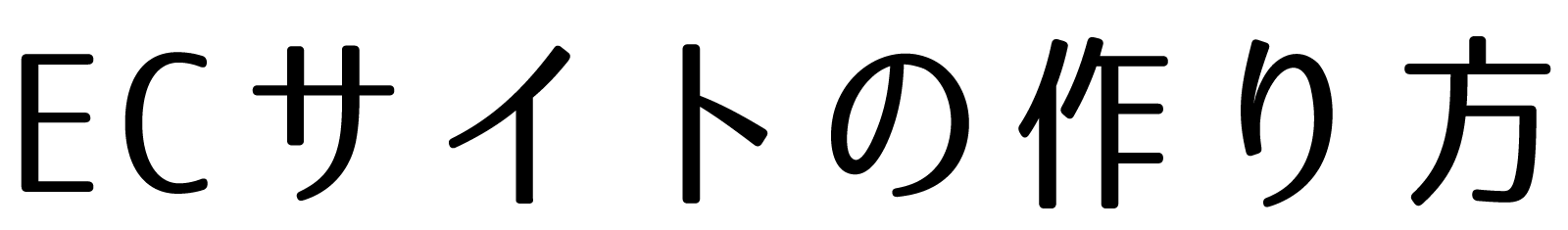
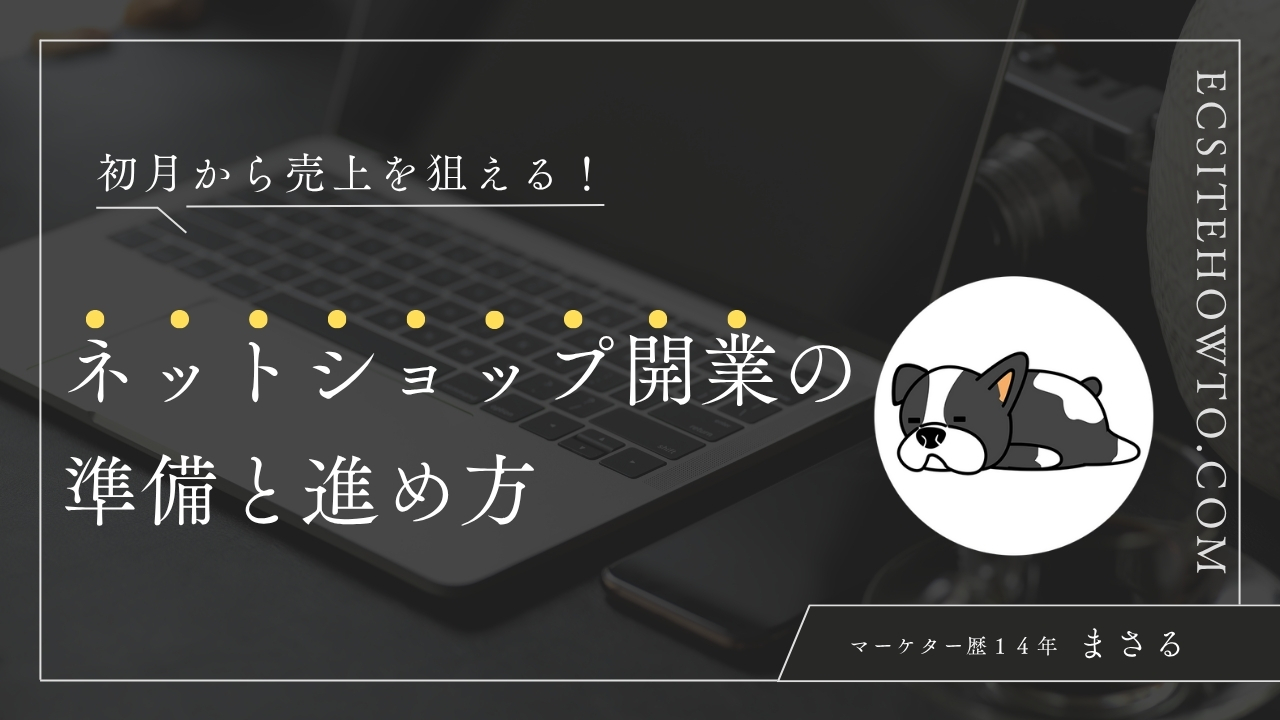



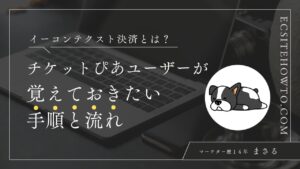


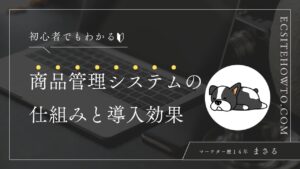

コメント