SaaSとクラウドの違いを理解せずに導入を進めると、無駄なコストや運用トラブルを招く恐れがあります。この記事では、各サービスの特徴や選定ポイントを専門家目線で分かりやすく解説しています。
クラウドサービスの全体像を押さえる

クラウドサービスとは、パソコンやスマートフォンがあれば、どこにいても仕事や作業ができるようにする仕組みのことです。とくにECサイトを運営する人にとって、クラウドをうまく使えるかどうかが、売上や作業のしやすさに大きく関わってきます。
クラウドとは何か?
クラウドとは、インターネットを使って、必要な機能やサービスを借りて使うことを指します。たとえば、商品のデータを保存したり、お客さまからの注文を受けたりするシステムを、自分で用意しなくても、クラウドならすでに準備されたものをすぐに使えます。
クラウドのいいところは、次のような点です。
- パソコンにソフトを入れなくても、ネットにつながれば使える
- 必要なときに必要な分だけ使える
- 最初に大きなお金をかけなくても始められる
- ソフトの更新やトラブル対応は、提供している会社がやってくれる
たとえば、ある洋服のECサイトでは、年末セールのときにお客さんのアクセスが急に増えました。でも、クラウドのサービスを使っていたおかげで、画面が止まったり、ページが見られなくなったりすることなく対応できたそうです。もし自分でサーバーを用意していたら、こうはいかなかったでしょう。
クラウドソフトウェアとは?
クラウドソフトウェアとは、インターネットを通じて使えるソフトのことです。たとえば、「Gmail」や「Googleスプレッドシート」などは、パソコンに入れなくてもブラウザから使えますよね? それがまさにクラウドソフトです。
これに対して、昔ながらのソフトは、CDなどで買ってパソコンに入れる必要がありました。そして使っているうちに古くなったら、自分で更新する必要がありました。
クラウドソフトなら、提供している会社が自動で新しいバージョンにしてくれるので、常に最新の状態で使えます。さらに、パソコンだけでなくスマホやタブレットからもアクセスできるので、外出先でも作業ができます。
実際に、知り合いの雑貨ショップのオーナーさんは、在庫管理のクラウドソフトを導入したことで、店にいなくても商品の数や注文の確認ができるようになり、かなり仕事がラクになったと言っていました。
クラウドソフトを使うことで、時間と手間を大きく減らすことができます。これからECサイトを始めたい人や、もっと便利に運営したい人には、ぜひ知っておいてほしい選択肢です。
SaaS・PaaS・IaaSの違いを理解する


クラウドサービスには大きく分けて「SaaS」「PaaS」「IaaS」の3つがあります。それぞれがカバーする範囲や目的は異なりますが、仕組みを理解すれば、導入時の判断や比較がぐっとしやすくなります。ここでは、実際の活用事例を交えながら、それぞれの違いと特徴をわかりやすく整理します。
各クラウドモデルの基本と特徴
まず、3つのクラウドサービスは以下のように分類されます。
| 分類 | 名称 | 利用者に提供されるもの | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| SaaS | ソフトウェアを提供 | アプリケーション全体 | すぐに使える。管理不要。 |
| PaaS | プラットフォームを提供 | 開発・実行環境 | 自社アプリを構築できる。 |
| IaaS | インフラを提供 | 仮想サーバーやネットワーク | 柔軟性が高いが運用が必要。 |
SaaSはすでに完成されたソフトウェアをそのまま利用できるため、導入がもっとも手軽です。メールや会計ソフト、チャットツールなどが代表例です。一方で、PaaSはアプリケーションの開発・実行環境を提供するため、開発部門のある企業に向いています。IaaSはサーバーやネットワークを自由に構成できるぶん、技術的な知識が必要ですが、細かなカスタマイズが可能です。
提供範囲・管理範囲の違い
この3つのモデルは、管理の範囲に違いがあります。たとえば、IaaSではサーバーやOSの管理をユーザーが行う必要がありますが、SaaSではすべてサービス提供側が行ってくれます。以下の図をご覧ください。
| 構成項目 | オンプレミス | IaaS | PaaS | SaaS |
|---|---|---|---|---|
| ハードウェア | 自社管理 | 提供元管理 | 提供元管理 | 提供元管理 |
| OS・ミドルウェア | 自社管理 | 自社管理 | 提供元管理 | 提供元管理 |
| アプリ開発 | 自社対応 | 自社対応 | 自社対応 | 提供元提供 |
| 保守・運用 | 自社対応 | 自社対応 | 一部提供元 | 提供元対応 |
たとえば、ある家具販売のEC企業では、受注システムはSaaSを、在庫連携部分だけをPaaSで独自開発しています。これは、全体を内製化せず、必要な部分だけを柔軟に構成できる「ハイブリッド利用」の好例といえます。
主な代表サービスの一覧
具体的なサービスをいくつか挙げておきます。
- SaaSの例:Google Workspace(ドキュメント・Gmail)、Chatwork、freee(会計)
- PaaSの例:Google App Engine、Heroku、Microsoft Azure App Service
- IaaSの例:Amazon EC2、Microsoft Azure、Google Compute Engine
これらを理解しておくことで、どのモデルが自社に合っているか、導入時の見極めがしやすくなります。特に、今後サービスを組み合わせて使う場面が増える中で、仕組みの違いを正しく理解することは、無駄なコストや手戻りを防ぐ上でも重要です。
クラウドサービスは「どれか一つを選ぶもの」ではなく、「どう組み合わせるか」が鍵になることを意識してみてください。
SaaSとクラウドの関係を整理する


「SaaSとクラウドはどう違うのか?」という質問は、ECサイトの相談を受ける中でも非常に多いです。両者は密接に関係していますが、まったく同じ意味ではありません。ここでは混同しがちな用語の整理と、理解の手助けになる実例を紹介します。
SaaSはクラウドの一種?
SaaS(Software as a Service)は、クラウドのサービス形態のひとつです。クラウドという大きな仕組みの中に、SaaS・PaaS・IaaSといったサービスモデルが存在します。つまり、SaaSはクラウドの一部であり、「クラウド=SaaS」ではないという点がポイントです。
たとえば、Googleドキュメントを使うとき、私たちはソフトをインストールせずに、インターネット上のアプリにアクセスしています。これがまさにSaaSです。一方、Amazon Web Services(AWS)のように、自分でアプリを構築したい人が使うのは、SaaSではなくIaaSやPaaSになります。
「クラウドって結局SaaSのこと?」という誤解を解くには、この“包含関係”をしっかり理解することが大切です。
「包含関係(ほうがんかんけい)」とは、あるものがもっと大きなグループの一部になっている関係のことです。
たとえば、SaaSはクラウドの中にふくまれているので、「SaaSはクラウドの一部」というふうに言えます。クラウドという“グループ”の中に、SaaS・PaaS・IaaSが“ふくまれている”というイメージです。
身近な例で言うと、
- フルーツ(クラウド)
- リンゴ(SaaS)
- パイナップル(PaaS)
- 洋梨(IaaS)
このような関係が「包含関係」です。


オンプレミス/クラウド/SaaSの位置づけ比較
オンプレミスとは、企業が自社の設備にサーバーやソフトを設置・管理して使う方法です。クラウドはその逆で、必要な機能を外部から借りる仕組みです。SaaSはそのクラウドの一部で、ソフトウェアをそのままサービスとして利用します。
以下の表をご覧ください。
| 項目 | オンプレミス | クラウド(IaaS/PaaS) | SaaS |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 高い | 中程度 | 低い |
| 導入スピード | 遅い | やや早い | 非常に早い |
| カスタマイズ | 自由度高い | 一部可能 | 限定的 |
| 運用負担 | 大きい | 中程度 | 小さい |
たとえば、あるアパレルEC企業は、在庫システムはクラウド(IaaS)で自社開発し、受注処理はSaaSを導入しています。このように、目的ごとに最適な方法を選ぶ「組み合わせ利用」も一般化しています。
ASPとの違いは何か?
SaaSとよく混同される言葉に「ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)」があります。どちらもインターネット経由でソフトを使う点では似ていますが、ASPは2000年代初頭に普及した古い仕組みで、サーバーごとに個別対応することが多く、運用の効率性や拡張性ではSaaSに劣ります。
SaaSは、すべての利用者が共通のソフト基盤を使う「マルチテナント型」が基本です。これにより、バージョンアップや機能追加も一斉に提供されるため、保守の手間がかからず、低コストで利用できます。
私の支援先でも、長年使っていたASP型システムをSaaSに切り替えたことで、保守費用が月額ベースで約3割削減され、営業担当者の業務スピードも向上しました。
混乱を避けるためには、「ASPは古い提供形態、SaaSは今の標準」という認識を持っておくことが大切です。言葉に惑わされず、本質的な仕組みの違いに目を向けて判断していきましょう。
ユースケースから選ぶSaaS活用例


SaaSは、「どんな業務に使うか?」によって選ぶべきサービスが大きく変わります。ここでは実際のビジネスシーンに合わせた活用例を紹介します。特にEC事業者や中小企業がすぐに導入できるツールも多いため、目的に応じた選定が成果に直結します。
ビジネスチャット・Web会議
チーム内のやりとりや社外との打ち合わせを円滑にするために、ビジネスチャットやWeb会議ツールは欠かせません。代表的なサービスには、Slack、Chatwork、Zoom、Google Meetなどがあります。
たとえば、私が支援しているある小売系EC企業では、全国に点在するパートスタッフとの連絡にChatworkを導入しました。これにより、電話やメールでは難しかった「リアルタイムな情報共有」が可能になり、在庫調整や緊急対応の精度が大きく向上しました。
これらのツールは、スマホやタブレットからも使えるため、現場でもすぐに連絡が取れるという点で非常に実用的です。
バックオフィス業務支援
日々の事務作業や管理業務を効率化するSaaSも数多く登場しています。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトは、領収書の読み取りから自動仕訳までこなしてくれるため、経理担当者の負担を大幅に軽減します。
また、SmartHRやジョブカンのような勤怠・労務管理ツールは、従業員の出勤状況や給与計算までクラウド上で一括管理できます。
以前、地方の飲食チェーン企業でSmartHRを導入した際、人事データの二重入力が不要になり、月末の集計作業が約半分の時間で終わるようになりました。こうした「効率の見える化」が、経営判断のスピードにも直結します。
業種特化型SaaSの紹介(医療、建設、小売など)
SaaSの中には、特定の業種に向けて設計されたサービスも多くあります。たとえば医療業界では、電子カルテや予約管理ができる「CLINICS」が有名です。建設業では、現場管理や日報提出をクラウドで行える「ANDPAD」などが普及しています。
EC業界では、受注・在庫・物流を一元管理できる「ネクストエンジン」や、商品情報の一括更新に強い「アシスト店長」などが代表的です。私が関わったアパレルECでは、これらの導入により、人の手で行っていたCSVのアップロードが不要になり、作業時間が週あたり6時間も削減されました。
SaaSは単に「便利なツール」ではなく、「業務を変えるきっかけ」になります。自社の課題と照らし合わせながら、合ったサービスを取り入れてみてください。
| 業種 | SaaSサービス名 | 主な機能 |
|---|---|---|
| 医療 | CLINICS | 電子カルテ、予約管理 |
| 建設 | ANDPAD、Photoruction | 現場管理、日報・工程共有 |
| EC・小売 | ネクストエンジン、アシスト店長 | 受注・在庫・商品情報の一括管理 |
必要なのは、すべてを変えることではなく、まずは“ひとつの改善”から始めることです。
SaaS導入の判断基準とチェックリスト


SaaSを導入する際は、「なんとなく便利そうだから」ではなく、自社にとって本当に必要かどうかを冷静に見極めることが重要です。ここでは、選定時に迷いやすいポイントを整理し、判断の軸となる基準とチェックリストをご紹介します。
自社に合うクラウドモデルの選び方
クラウドサービスは、SaaS・PaaS・IaaSのいずれが適しているかで、業務の流れや導入コストに大きく差が出ます。たとえば、自社でソフトを一から開発する必要がなければ、まずはSaaSから検討するのが最も効率的です。すでに完成されたサービスを「そのまま使う」形なので、導入スピードも早く、運用の負担も小さくなります。
逆に、既存のシステムとどうしても連携が必要だったり、業務が複雑な場合は、柔軟性の高いPaaSやIaaSも視野に入れるべきです。判断のポイントは、「既存の仕組みをどこまで活かしたいか」と「社内にどれだけITのリソースがあるか」です。
セキュリティ・コスト・運用負担の視点
SaaS導入の際に必ずチェックしておきたいのが、セキュリティ体制とコスト構造です。どれだけ機能が優れていても、情報漏えいや障害のリスクが高ければ意味がありません。
信頼性を見極めるためには、以下の点を確認しましょう。
- 通信やデータの暗号化がされているか
- ISO27001などの認証を取得しているか
- データの保存場所やバックアップ体制
- サポート体制とトラブル時の対応スピード
また、月額料金が安く見えても、ユーザー数の追加やオプション機能でコストが膨らむケースもあります。特に「無料プランから有料へ切り替えるタイミング」で、予算オーバーになりやすい点には注意が必要です。
導入前に確認すべきポイント一覧
SaaSを導入する前に、以下の順で確認しておくと安心です。
- 解決したい業務上の課題を明確にする
- 実際に利用する人のITスキルや運用体制を確認する
- 業務フローとSaaSの相性を検討する
- 社内の承認プロセス(稟議・決裁)を整えておく
- サービス停止時やトラブル時の対応策を考えておく
実際に、ある食品メーカーでは、最初に目的を「出荷ミスの削減」に絞ってSaaSを選びました。結果、過剰な機能にお金をかけることなく、現場にしっかりなじむツールを導入できています。
導入の成功は、選定前の準備と理解にかかっています。まずは「なぜ導入するのか」をチーム内で共有し、必要最低限の条件を洗い出すことから始めてみてください。思い込みで選ばず、“使えるサービス”を見つけることが、成果を生む近道です。
焦らず、自社に本当に必要なサービスかどうかを見きわめてくださいね!
SaaSとクラウドの今後と注目トレンド


SaaSとクラウドサービスは、業務の効率化だけでなく、企業の成長戦略にまで影響を与える存在となっています。現在は「導入すべきかどうか」ではなく、「どのように組み合わせて最大化するか」が問われる時代です。ここでは、押さえておきたい3つの重要なトレンドを紹介します。
ハイブリッドクラウドとSaaS連携の可能性
ハイブリッドクラウドとは、社内システム(オンプレミス)とクラウドサービスを組み合わせて活用する方法です。これにより、既存の資産を活かしながら、クラウドの柔軟性や拡張性を取り入れることができます。
ある物流企業では、受注処理はクラウドSaaSで行い、顧客管理は社内サーバーに残すという体制を取りました。SaaSと社内システムをAPIでつなぐことで、全体の情報連携がスムーズになり、処理速度が約30%向上したという結果も出ています。
このように、クラウドとSaaSは「切り替え」ではなく「共存」させることで、新しい業務設計が可能になります。
AI・自動化との融合
近年は、SaaSにAIやRPA(自動化ロボット)が組み込まれるケースも増えています。たとえば、チャットボットによる問い合わせ対応や、AIによる売上予測などがすでに実用化されています。
ECサイト向けのSaaSでも、AIが過去の購入履歴から「次に買いそうな商品」を自動で表示する機能が増えています。私が関わったアクセサリーショップでは、この機能を活用したところ、関連商品の購入率が平均1.4倍にアップしました。
これからのSaaSは、単なる「業務を支えるツール」ではなく、「業務を賢く動かすパートナー」としての役割が求められます。
法規制・データ保護の観点
SaaSは便利な反面、データの保管場所や取り扱い方に注意が必要です。特に個人情報や取引データを扱うEC事業では、各国の法規制やプライバシー保護法への対応が欠かせません。
たとえば、欧州のGDPR(一般データ保護規則)や、日本の個人情報保護法に対応していないサービスを使うと、法的リスクが生じる可能性があります。また、クラウド上に保存されたデータが海外のサーバーにある場合、その国の法律が適用されることもあるため、利用規約や保管場所の明記は必ず確認しておきたいポイントです。
万が一のトラブルを避けるためにも、契約前に「どのようにデータが保護されているか」「万が一の際の対応体制があるか」を細かくチェックすることをおすすめします。
時代とともに進化するSaaSとクラウド。その本質を正しく理解し、自社の成長にどう活かせるかを考えることが、これからの導入判断における重要なカギとなります。まずは身近な業務から、トレンドを踏まえた見直しをしてみてはいかがでしょうか。
よくある質問
- GoogleはSaaSですか?
-
はい、Googleの多くのサービスはSaaS(サース)にあたります。たとえば、Gmail、Googleドキュメント、Googleスプレッドシートなどは、インターネットを通じて提供されるソフトウェアであり、ユーザーは自分のパソコンにインストールすることなく利用できます。これらはすべてGoogleが管理・保守を行い、常に最新の状態で利用できるため、典型的なSaaSの形態といえます。
- ソフトウェアとSaaSの違いは何ですか?
-
ソフトウェアは一般的にパソコンにインストールして使うものを指し、管理や更新は利用者自身が行います。一方、SaaSはインターネット上で提供され、ブラウザを使って利用する形が基本です。SaaSは提供会社がすべて管理するため、ユーザーはインストールやアップデートの手間がありません。手軽さと自動管理がSaaSの大きな違いです。
- SaaSとWebサイトの違いは何ですか?
-
Webサイトは主に情報の閲覧を目的としたページで、ニュースサイトや企業サイトなどが該当します。一方、SaaSは「利用者の操作によって動作する」アプリケーションであり、たとえばクラウド会計ソフトやチャットツールのように、業務の中で直接使う機能を提供するのが特徴です。見た目は似ていても、役割と仕組みがまったく異なります。
- SaaSの代表例は?
-
代表的なSaaSには、Gmail、Google Workspace、Chatwork、Zoom、freee(会計)、マネーフォワード、Salesforceなどがあります。いずれもインターネットを通じて提供され、ソフトをインストールせずに使えることが特徴です。業務の効率化やコスト削減を目的に、企業や個人で幅広く活用されています。
- SaaSの欠点は何ですか?
-
SaaSの欠点としてよく挙げられるのは、インターネット接続がないと使えない点と、カスタマイズの自由度が低いことです。また、クラウド上にデータを預けるため、情報漏えいなどセキュリティ面の不安を持つ企業もあります。契約内容によってはランニングコストが割高になる場合もあるため、選定には注意が必要です。
SaaSとクラウドの違いを正しく理解すれば、自社に最適な選択肢が見えてきます。導入前に整理すべきポイントを押さえ、業務に合ったサービス選定につなげていきましょう。



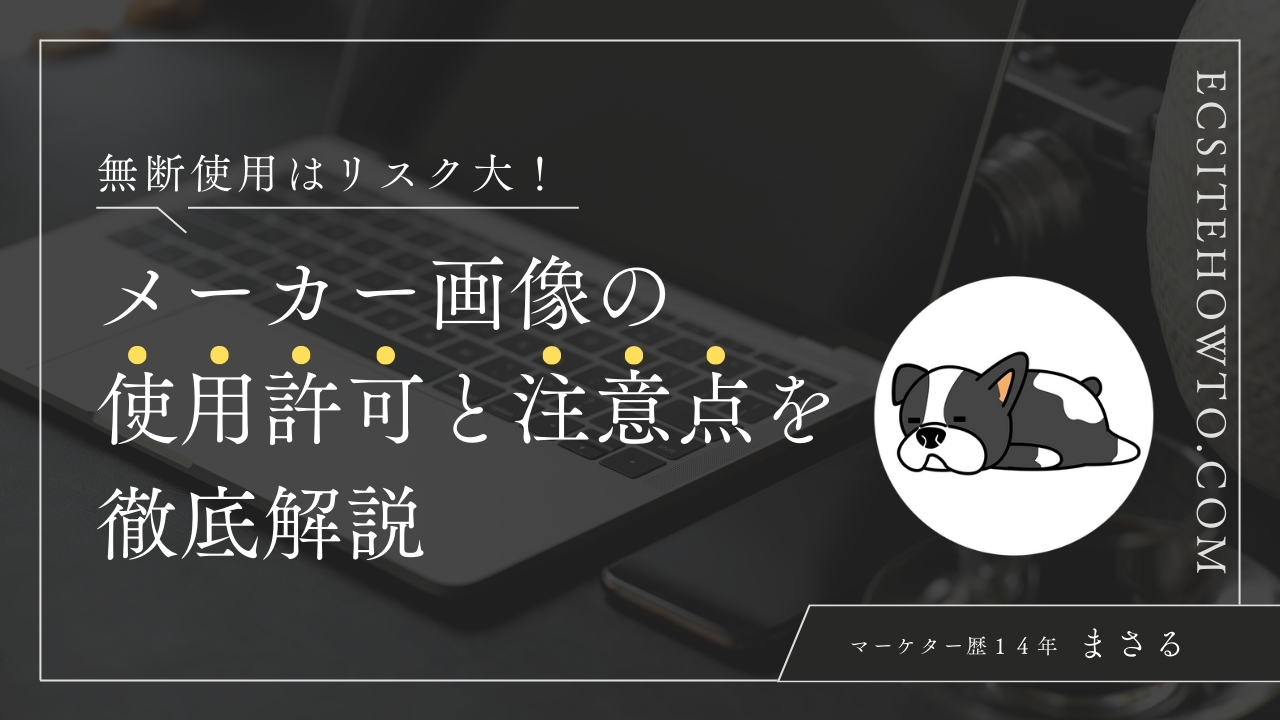

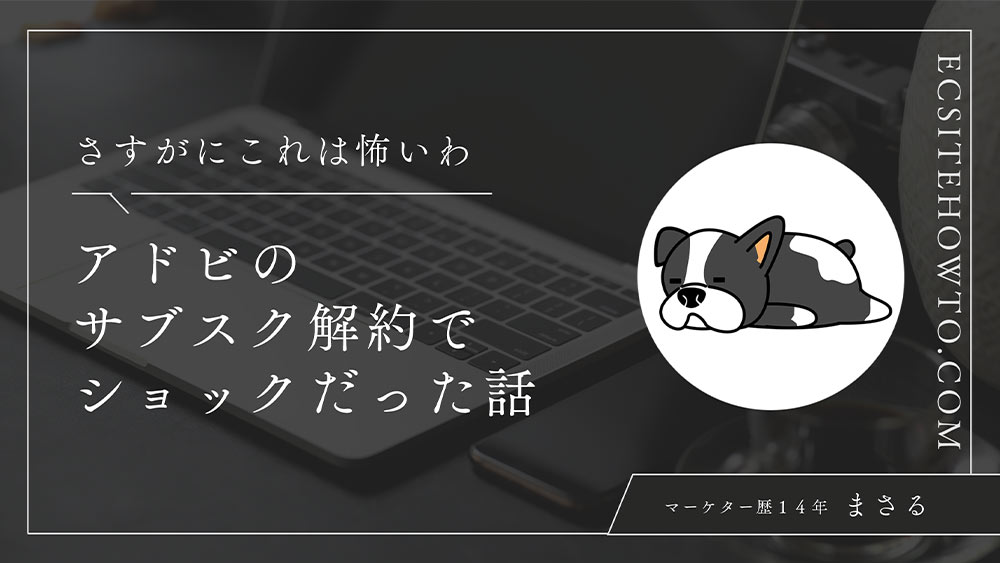
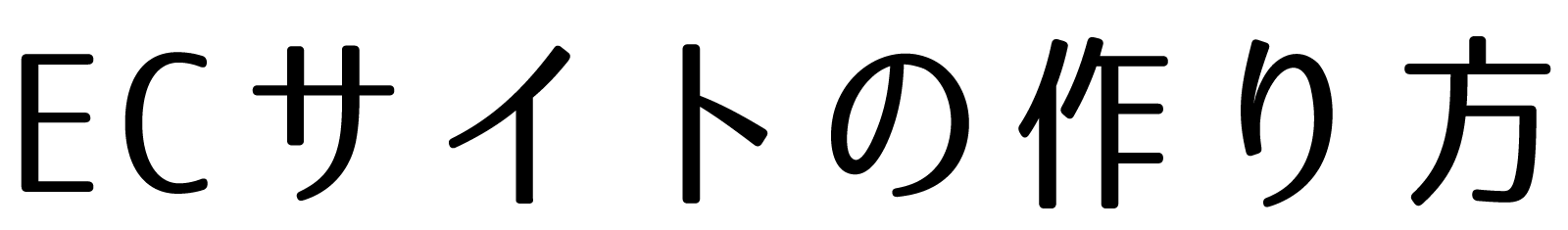


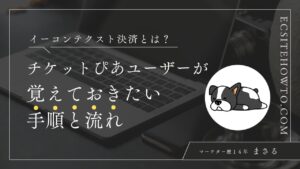


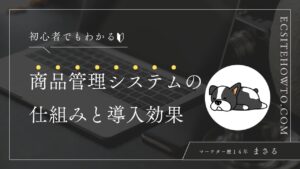

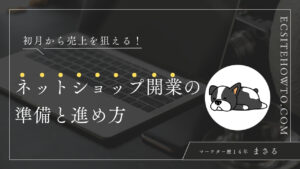
コメント