越境ECとはどのような仕組みか、なぜ今注目されているのかを明確に解説します。個人や中小企業が越境ECを活用して売上を伸ばすための実践的な情報を提供します。
越境ECとは何か?基本と読み方

日本国内のビジネスが新たな販路を求めて海外に目を向ける中、「越境EC」という言葉が急速に注目を集めています。特に中小企業や個人事業主にとって、グローバル市場への足がかりとして大きな可能性を秘めたモデルです。このパートでは、越境ECの基本的な意味や仕組み、そして言葉の読み方や英語表現までを丁寧に解説します。
越境ECの意味と仕組み
越境ECとは、「国を越えて商品やサービスをインターネット上で売買する電子商取引」のことを指します。たとえば、日本国内にある企業がアメリカの消費者に自社製品をネット経由で販売する、といったケースが典型的です。
仕組みとしては、主に以下の3つに分けられます。
- 商品掲載:自社サイトやAmazon・Tmallなどのモールに出店
- 注文受付と決済:多通貨対応やクレジット決済、現地決済をサポート
- 海外配送とカスタマー対応:EMS(国際スピード郵便)や現地倉庫を利用し、現地語サポートも整備
特に2020年以降は、コロナ禍をきっかけにリアルな国境を越える移動が制限され、オンラインでの越境取引が急成長しました。物流インフラの整備や海外モールの参入ハードルが下がったことで、個人規模でも参入しやすくなっています。
なお、「越境EC」は「えっきょうイーシー」と読みます。「越境」とは国境を越えることを意味し、もともとは移動や移住に使われる言葉でした。それが現在では、ビジネスやデジタル分野でも「越境マーケティング」や「越境EC」といった形で広く使われています。実際のビジネス現場では、「クロスボーダーEC(Cross-border EC)」という表現もよく用いられています。
英語ではどう表現する?
英語では「Cross-border eCommerce(クロスボーダー・イーコマース)」または「Cross-border EC」という表現が一般的です。特に欧米や中国向けの資料作成では「cross-border」という語を使用することで、よりスムーズに意図を伝えることができます。
たとえば、あるアパレル企業が越境ECを導入する際、英語版のWebサイトには「We offer cross-border eCommerce shipping to over 50 countries(当社は、50カ国以上への越境EC配送サービスを提供しています)」と明記し、海外の顧客から信頼を得るといったケースがあります。
越境ECの本質は、「距離や言語の壁を越えて、価値を届けること」です。読み方や言葉の意味を正しく理解しておくことは、実務においても重要な一歩となります。
この基本をおさえておくと、成長市場や活用事例が見えてきて、自社の可能性もより明確になりますよ。
越境ECの市場と企業動向


越境ECは今や一部の大企業だけでなく、中小企業や個人にとっても現実的な成長戦略となっています。ここでは、国内外の市場規模、有名企業の取り組み、そして売れ筋ジャンルまで、最新の動向をわかりやすく紹介します。
国内外の越境EC市場規模
世界の越境EC市場は年々拡大を続けており、2024年時点でその規模は約5兆ドルとも言われています。特にアジア市場、とくに中国・東南アジアの成長は目覚ましく、日本企業にとっても魅力的なターゲットです。
日本からの越境EC輸出額は、2022年にアメリカ向けが1.2兆円、中国向けが2.1兆円に達しました(経済産業省データ)。注目すべきは、インバウンド需要の反動で「日本製品=高品質」のイメージが強まり、現地の消費者からの信頼が厚い点です。
実際、円安や物流の改善も追い風となり、小規模EC事業者でも越境販売を始める事例が増えています。D2CモデルやSNS経由での直接販売も成長中です。
D2C(ディーツーシー)とは、Direct to Consumer(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)の略で、メーカーやブランドが仲介業者を通さず、直接消費者に商品を販売するビジネスモデルのことです。自社ECサイトやSNSを活用して、商品企画から販売・サポートまで一貫して行うのが特徴です。
越境ECを活用する有名企業一覧
越境ECに積極的な日本企業は少なくありません。たとえば以下のような企業が代表的です。
- ヤーマン:中国のTmall Globalでライブコマースを活用し、売上を大幅に伸ばしました
- ニトリ:台湾・中国・韓国に専用ECサイトを展開し、海外売上比率を急拡大中
- 無印良品:アジア各国で越境EC対応を強化し、公式アプリとも連携
また、楽天やBASEを活用して個人レベルで越境販売を行う事例も増えており、始めるときのハードルは確実に低下しています。
売れている商品・人気ジャンルランキング
越境ECで人気のある商品は、地域によって異なる傾向がありますが、日本製の商品は総じて信頼性が高く、一定の需要があります。以下は代表的なジャンルです。
| 人気ジャンル | 理由 |
|---|---|
| 化粧品・スキンケア | 安全性・品質の高さ、パッケージデザインの良さ |
| 健康食品 | 成分表記が明確、信頼できるブランドが多い |
| ベビー用品 | 日本製は安心というイメージが強い |
| 文房具・雑貨 | 独自性があり、プレゼント需要も高い |
| アニメグッズ | サブカルチャー人気により世界中で売れている |
越境ECを成功させるには、こうした市場や消費者のニーズを的確に読み取ることが不可欠です。まずは自社商品がどの国でどのように受け入れられそうか、実際の販売データや現地レビューを調べることから始めましょう。
越境ECのビジネスモデルと活用方法


越境ECを始める際には、自社サイトで販売するのか、既存のモールに出店するのか、それとも代行業者を使うのかといった運営スタイルを決めることが重要です。それぞれの方式には異なるメリットと注意点があり、事業規模や販売国に応じた選択が成果を左右します。
自社EC型、モール出店型、代行型の違い
越境ECには主に以下の3つのビジネスモデルがあります。
| モデル | 主な特徴 | 向いている事業者 |
|---|---|---|
| 自社EC型 | 独自サイトで運営、ブランディング重視 | ブランドを確立したい企業 |
| モール出店型 | 集客力があるモール(Amazon・Tmall・Shopeeなど)に出店、販路拡大しやすい | 初心者〜中堅事業者、集客力を活用したい事業者 |
| 代行販売型 | 販売〜発送まで外部委託 | 海外対応のノウハウがない企業 |
たとえば、日本のある化粧品メーカーは、Tmall Globalに出店して中国の若年層女性向けに商品を販売しました。ライブ配信も組み合わせて、半年で売上が3倍に成長しました。一方で、海外向けの自社ECを構築し、独自ブランドの世界観を前面に出して売上を伸ばしているアパレル企業もあります。
個人・法人どちらも始められる?
越境ECは法人だけのものではありません。実際に、個人事業主や副業としてスタートする人も少なくありません。たとえば、メルカリShopsやBASEと連携して海外発送に対応したり、eBayを使って海外にアンティーク商品を販売している例も見られます。
ただし、個人であっても以下のポイントは事前に整えておく必要があります。
- 英語や現地語の商品説明・カスタマー対応の準備
- 国際配送と返品対応の仕組み
- 税関・関税のルール理解と対応
最初は小ロットから始め、慣れてきたら法人化を目指すのもよくある流れです。
eBay(イーベイ)とは、アメリカ発の世界的なオンラインオークション&マーケットプレイスサイトです。個人も企業も商品を出品でき、世界190以上の国と地域で取引されています。新品だけでなく中古品やレアなコレクター商品も多く出品されており、越境ECの入り口としても人気です。
越境ECと通常ECの違いとは
国内向けECと越境ECでは、基本的な仕組みは似ていますが、対応すべき領域は格段に増えます。たとえば以下の点が大きく異なります。
- 言語と通貨の違い:現地語対応が信頼感に直結
- 物流と配送期間:国をまたぐ分、配送の遅延リスクが高い
- 法律と規制:販売可能な商品、表記義務、輸入制限など
たとえば、日本では販売できる健康食品が、海外では禁止成分が含まれていたり、パッケージ表示が現地ルールに合っていないと販売停止になることもあります。
越境ECには国内ECにない複雑さがありますが、対応を丁寧に整えれば、その分だけ売上の伸びしろも大きくなります。自社に合ったモデルを見極め、小さく始めて確実に育てていく姿勢が成功の鍵となります。
越境ECの始め方ガイド


越境ECを始めるには、明確なステップと現地対応への準備が欠かせません。個人・法人どちらの立場でも取り組める時代だからこそ、自分のリソースや目標に応じた進め方を選ぶことが重要です。このパートでは、個人と法人の始め方、そして頼れる支援サービスまでを具体的に紹介します。
個人で始める方法とおすすめの手順
副業や小規模ビジネスとして越境ECに取り組む個人は、初期コストを抑えつつ段階的にスキルと販路を広げるのが理想です。以下の手順が一般的です。
- 販売プラットフォームを選ぶ(例:eBay、Etsy、Shopee)
- 販売する商品を決める(例:日本製文具、アニメグッズ)
- アカウント作成と本人確認
- 商品ページ作成(英語対応)と価格設定
- 海外発送方法の選定(例:EMS、国際eパケット)
- 発送・顧客対応・レビュー管理
最初は数件の注文でも問題ありません。たとえば、日本の伝統工芸品や日用品など、あなたの身近にある“魅力的だけど海外では手に入りにくい商品”を選んで、まずは出品してみましょう。完璧な準備よりも、まず一歩を踏み出すことが重要です。経験を重ねるうちに、商品ごとの反応やニーズが見えてきます。そこから改善を繰り返していけば、リピーターがつき、安定した売上につなげることができます。
法人が参入する際のポイント
法人が越境ECを導入する場合は、ブランディングと長期戦略を視野に入れる必要があります。特に以下の3点は初期段階で押さえるべきです。
- ターゲット国と市場調査:文化・法律・競合分析をセットで実施
- 販売チャネルの明確化:自社サイト構築 or 海外モール出店かを選定
- 越境対応体制の構築:多言語カスタマー対応、関税処理、現地決済への対応
たとえば、アジア市場に進出したいと考えている場合は、Tmall Globalなどの越境ECモールを活用するのが有効です。その際には、現地の法律や食品・薬事に関する規制をしっかりと確認し、必要に応じて専門コンサルタントの支援を受けることをおすすめします。準備に時間をかけた分だけ、販売後のトラブルを防ぐことができ、長期的な販路拡大にもつながります。特に東南アジア市場では、日本製品への信頼が厚く、早期に成果が出やすい傾向があります。
越境ECに強い代行会社・支援サービス
越境ECの最大の壁は、言語、物流、法規制の3つです。これらをスムーズにクリアするには、実績ある支援サービスの活用が有効です。
代表的な代行・支援サービスには以下のようなものがあります。
- ジグザグ(WorldShopping BIZ):既存の自社サイトに越境対応を追加できる
- BeeCruise:モール出店から現地マーケティングまでを包括支援
- ZenMarket:日本の商品を世界中に届ける購入代行モデル
どのサービスも、最初からすべてを自力で構築するのが難しい中小企業や個人にとって強い味方になります。
越境ECは、一歩踏み出せば誰にでもチャンスが広がる市場です。無理にすべてを抱え込まず、頼れる外部リソースと連携することで、効率的に成果を出すことができます。
まずは一つの商品から、小さく始めてみることをおすすめします。
越境EC成功のコツと失敗事例


越境ECでは、国内ECと同じ手法がそのまま通用するとは限りません。現地ニーズの誤認や規制対応の甘さが失敗につながるケースも多くあります。このパートでは、成功のために欠かせない視点と、よくある落とし穴を具体的に解説します。
海外ニーズの把握と商品選定
売れる商品は、国や文化によって大きく異なります。たとえば、日本で人気のある機能性商品でも、海外では「何に使うのか分からない」と敬遠されることがあります。
まず大切なのは、「現地の消費者が何に価値を感じているか」を調べることです。SNSの口コミ、レビューサイト、越境ECモール内の売上ランキングなどを活用すれば、トレンドを把握できます。
さらに、以下の視点で商品を選定すると成果が出やすくなります。
| 観点 | 理由・特徴 |
|---|---|
| 日本特有の商品 | 海外では希少で価値が伝わりやすい |
| 汎用性の高い商品 | 言語や文化が違っても使いやすく、受け入れられやすい |
| 小型・軽量商品 | 配送コストが抑えられ、返品リスクも低くなる |
| 消耗品・定期購入品 | リピーターがつきやすく、LTV(1人の顧客が、ある企業にもたらす総利益のこと)が高くなる可能性がある |
販売前に、現地のモニターに商品を試してもらう簡単なリサーチを挟むだけでも、商品選定の精度は大きく変わります。
言語・決済・物流の最適化
商品が良くても、購入までの体験がスムーズでなければ離脱されてしまいます。特に重要なのが「言語」「決済方法」「配送スピード」の3点です。
| 項目 | 対応方法の例 |
|---|---|
| 言語 | 現地語による商品説明、FAQ、返品対応ページの整備 |
| 決済 | PayPal、Alipay、現地クレジット決済への対応 |
| 物流 | EMS、DHL、現地倉庫の活用、追跡可能な配送の選択 |
たとえば、日本のハンドメイド商品を販売していた事業者は、英語翻訳をAIに任せていたことで誤訳が多発。レビュー評価が下がった結果、販売数も激減しました。信頼を得るには、細部まで丁寧に整えることが大切です。
法規制や関税リスクへの備え
越境ECでもっとも見落とされがちなのが、各国の法規制や関税への対応です。内容物によっては輸出入が禁止されていたり、現地のパッケージ表示義務に違反してペナルティを受けることもあります。
以下のような準備をしておくと安心です。
- 販売対象国の「禁制品リスト」を確認
- 輸出入時に必要な成分表示やラベルの形式を調査
- 関税がかかる商品かどうか、事前に明示しておく
とくに食品・化粧品・医療器具などは各国のルールが非常に厳格で、対応を怠ると販売停止に繋がる可能性があります。
成功のためには、「相手国の立場になって考える」ことが何より大切です。ひとつひとつ丁寧に整えていけば、信頼とリピートは自然とついてきます。まずは小さな取引からでも、確実な体制づくりを意識して始めましょう。
禁制品リストは、各国の税関や郵便局の公式サイトで確認できます。たとえば、
・アメリカ → U.S. Customs and Border Protection(CBP)公式サイト
・中国 → GACC(中国海关总署)公式サイト
・日本から発送 → 日本郵便
日本郵便のサイトでは、送り先の国を選ぶと、禁制品や制限品が一覧で表示されるのでとても便利です。まずはそこを確認するのがおすすめです。
越境ECを成功させるための実践戦略


越境ECは誰にでもチャンスがありますが、成功するには場当たり的な施策では不十分です。中小企業、個人、デジタル施策のそれぞれにおいて、確実に成果を出すために押さえるべき実践的な戦略を紹介します。
中小企業が海外進出で成功するには
中小企業が越境ECで成果を出すには、「ローカライズ」「段階的な検証」「外部リソースの活用」が鍵になります。
まず重要なのは、ターゲット国に合わせた情報設計です。商品説明は現地語に翻訳するだけでなく、「現地でどう使われるか」を想定して見せ方を最適化する必要があります。言い換えれば、“自社商品を海外の消費者がどう価値付けるか”を逆算して設計することです。
次に、いきなり全商品・全市場に展開しないこと。1〜2カ国、1〜2商品に絞り、テスト販売を行いながらPDCAを回していくスタイルがリスクも少なくおすすめです。
加えて、通関・物流・カスタマー対応といった業務は越境ECに強い支援会社と連携し、社内工数を抑えながら質の高い運用を目指すべきです。自社で抱え込みすぎると、継続できないというケースが多く見られます。
個人から起業に発展させる方法
個人が越境ECを始めて事業化するには、「ニッチ商品の選定」「信頼性の構築」「小さく始めて伸ばす姿勢」が成功の道筋になります。
越境ECにおいて、量産型商品よりも個人の目利きでしか扱えない商品や文化的背景のある商品が強みになります。日本特有の雑貨や、こだわりのハンドメイド品などは、海外市場で評価されやすい傾向にあります。
販売初期は、丁寧な顧客対応やレビュー集めを通じて信頼を積み重ねることが何よりも大切です。商品ページの英語表記、発送連絡、梱包の丁寧さなど、地道な対応がリピートにつながります。
副業レベルでも月商数万円から始めることは可能ですが、売上が伸びてきた段階で法人化し、SNS運用や広告投資、商品展開の幅を広げていくことが継続成長につながります。
ライブコマースやSNSを活用した展開方法
現代の越境ECでは、「商品力」だけで勝負するのは難しくなっています。SNSとライブコマースを活用したプロモーション戦略は、集客・信頼構築・購入導線のすべてを効率的にこなす重要な手法です。
特にアジア圏では、Tmall GlobalやShopeeなどでのライブ配信による実演販売が購買行動に大きな影響を与えています。商品説明だけでなく、使用感やレビューをリアルタイムで伝えることができるため、顧客との心理的距離を一気に縮めることが可能です。
また、InstagramやTikTokを活用してフォロワーを顧客化する流れをつくることも有効です。以下のような導線設計がポイントになります。
- 商品の魅力をストーリーズやリール動画で紹介
- プロフィールリンクから自社ECまたはモールに誘導
- フォロワー限定クーポンやライブ配信で購買を促進
デジタル施策を軽視せず、“売る前の信用づくり”をどう積み上げるかが、売上を左右する時代です。使い慣れたSNSからスタートし、少しずつ販促手段を広げていきましょう。
越境ECをさらに深く知るために


越境ECは始めるだけでなく、継続的に学びながら改善を重ねていくことが重要です。このパートでは、知識を深めるために役立つ用語、業界の最新トレンド、そして信頼できる学習リソースを紹介します。
よく使われる用語集とその意味
越境ECでは、専門用語が頻繁に登場します。意味を曖昧にしたままでは判断ミスにもつながるため、基本的な用語はしっかり押さえておきましょう。
| 用語 | 日本語訳 |
|---|---|
| DDP(Delivered Duty Paid) | 関税込み持込渡し |
| D2C(Direct to Consumer) | 消費者への直接販売 |
| SKU(Stock Keeping Unit) | 在庫管理単位 |
| Tmall Global | 中国向け越境ECモール |
| バーチャル倉庫 | 実在しない委託型倉庫管理方式 |
知らない用語が出てきたら、その場で必ず調べる習慣をつけておくと、越境ECの実務レベルでの理解がぐっと深まります。
越境ECに関する最新トレンド
越境ECは急速に変化している業界です。特に注目すべきは以下のようなトレンドです。
| トレンド | 特徴 |
|---|---|
| ライブコマース | インフルエンサーが配信、購入意欲を短時間で喚起。中国やASEAN市場では主流化。 |
| D2C型ブランド | SNSを活用してファンと直接つながり、高単価でも成約 |
| エコ対応商品の需要増 | 欧米を中心にサステナブル商材への関心が高まっている |
| モバイルファースト消費 | スマホ1台で購入完結、UI最適化が重要 |
変化の速い分野だからこそ、SNSや業界メディアを通じて情報を日々アップデートする姿勢が求められます。
越境ECを学べる書籍・サイト・セミナー
本や専門サイト、リアルの勉強会を活用することで、表面的な情報にとどまらない深い学びが得られます。例えば以下のようなものがあります。
書籍
- はじめての越境EC・海外Webマーケティング|徳田 祐希 (著)
- 越境EC&海外Webマーケティング“打ち手”大全| 徳田祐希 (著)、中村岳人 (著)、森田尚志 (著)
Webサイト
- 日本貿易振興機構(JETRO)
- eccLab(eコマースコンバーションラボ)
セミナー・展示会
- JETRO主催の越境ECオンラインセミナー
- イーコマースフェア東京
知識は一度得たら終わりではなく、常に更新されていくものです。学び続けることで、自社のビジネスにも柔軟性と強さが生まれます。信頼できる情報源を定期的にチェックする習慣を、今日から始めてみましょう。
まとめ


越境ECは、単なる海外販売ではなく、「自社の商品やブランドを世界に届けるための戦略的なチャレンジ」です。市場動向、ビジネスモデル、立ち上げ手順、成功事例までを一つ一つ理解すれば、自信を持って第一歩を踏み出すことができます。
これまで紹介してきたように、越境ECにはさまざまなスタイルがあります。たとえば、自社でECサイトを立ち上げてブランドの世界観を発信する方法もあれば、AmazonやTmall Globalなど既存のモールを活用して集客力を借りる方法もあります。リソースや目的に応じて最適な手法を選び、少しずつ仕組みを整えていくことが大切です。
また、現地のニーズ調査や文化理解は欠かせません。たとえ品質に自信がある商品であっても、「その価値がどう伝わるか」は国によってまったく異なります。レビューやSNS、現地パートナーの声を活用して、常にアップデートする姿勢が求められます。
一方で、物流や言語、税制など、国内ECにはない複雑さも存在します。ただし、それらの壁を乗り越えるための支援サービスやツールも年々進化しています。最初からすべて自分で完璧に行おうとせず、外部リソースをうまく取り入れることも成功のポイントです。
越境ECは、努力の分だけ「世界中にファンをつくれる」ビジネスです。最初は小さな取引からでもかまいません。この記事を参考に、まずは一歩踏み出してみてください。
行動した人から、海外市場という新たなチャンスを掴むことができます!
よくある質問


- 越境ECとECの違いは何ですか?
-
ECは国内向けのネット通販全般を指しますが、越境ECは「国を越えた」取引を行うECです。具体的には、日本からアメリカや中国など海外の消費者に商品を販売する場合が該当します。物流、決済、言語、法規制などが国ごとに異なるため、対応がより複雑になります。
- 越境ECプラットフォームとは何ですか?
-
越境ECプラットフォームとは、海外の顧客向けに商品を販売できる仕組みを提供するネットモールや販売システムのことです。代表的なものには「Tmall Global」「Amazon Global」「Shopee」などがあり、現地語対応や決済・物流支援など、越境に必要な機能が整備されています。
- 越境ECとはどのような事業内容ですか?
-
越境ECは、インターネットを通じて日本国内から海外の個人・企業へ商品やサービスを販売する事業です。販売方法には、自社サイトや海外モールへの出店、現地パートナーとの連携などがあります。国境を超えるため、言語対応、関税、法律面への配慮も事業の一部となります。
- 越境ECの最大手はどこですか?
-
越境EC分野の最大手としては、中国向けで「Tmall Global」、グローバル展開では「Amazon Global」、東南アジアでは「Shopee」や「Lazada」が有名です。それぞれ対象地域や出店条件が異なり、販売戦略に応じて選ぶ必要があります。Tmall Globalは特に日本企業の進出例が多く注目されています。
- ECプラットフォームとECとは何が違うの?
-
ECは「電子商取引」全体を意味する広い概念で、通販サイト・アプリを含む全体の仕組みです。一方、ECプラットフォームはその中でも、複数の出店者が商品を販売できる場を提供するサービス(例:Amazon、楽天)を指します。つまり、プラットフォームはECを実現するための手段の一つです。
- 越境ECはどの国を対象にしているのですか?
-
越境ECに「特定の国」はありません。越境ECとは国境を越えたEC取引全体を指すため、日本からアメリカ、中国、東南アジア、ヨーロッパなど、さまざまな国が対象になります。どこの国と取引するかは、取り扱う商品や狙う市場によって異なり、戦略的に選ぶ必要があります。
越境ECは、正しい知識と準備があれば誰でも成果を出せる分野です。本記事を参考に、自社や個人の強みを活かした海外展開にぜひ挑戦してみてください。



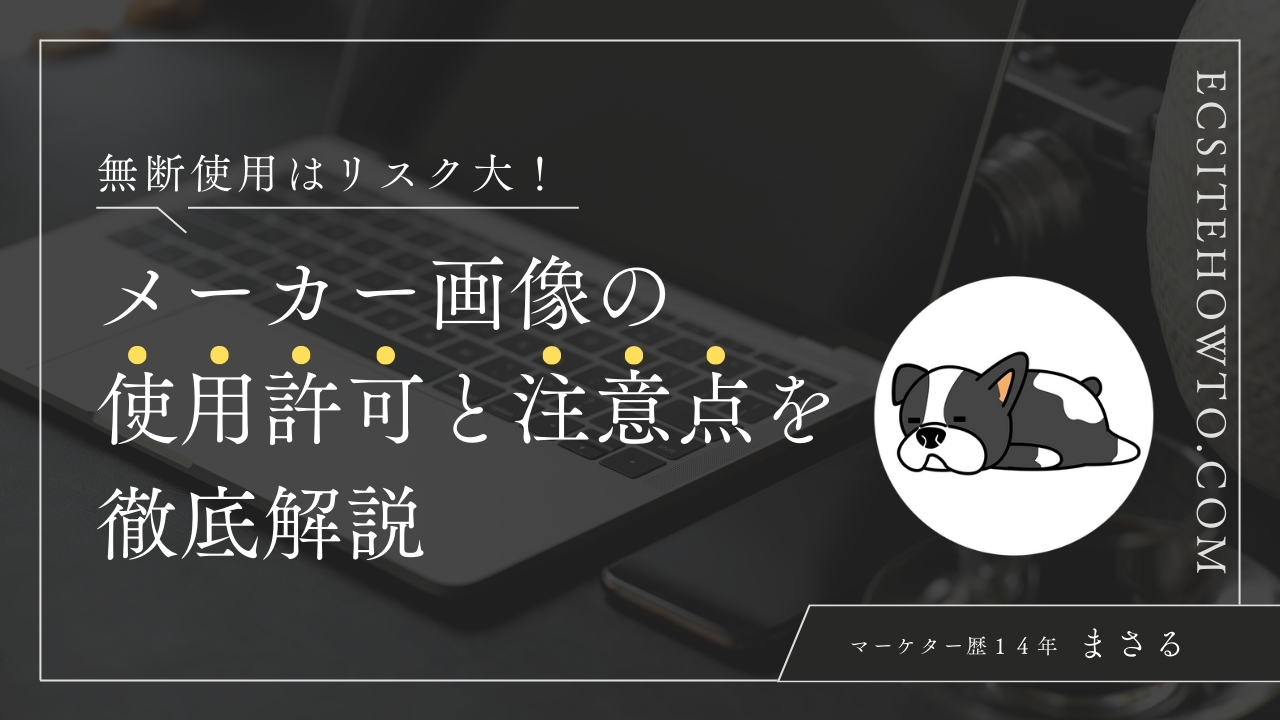

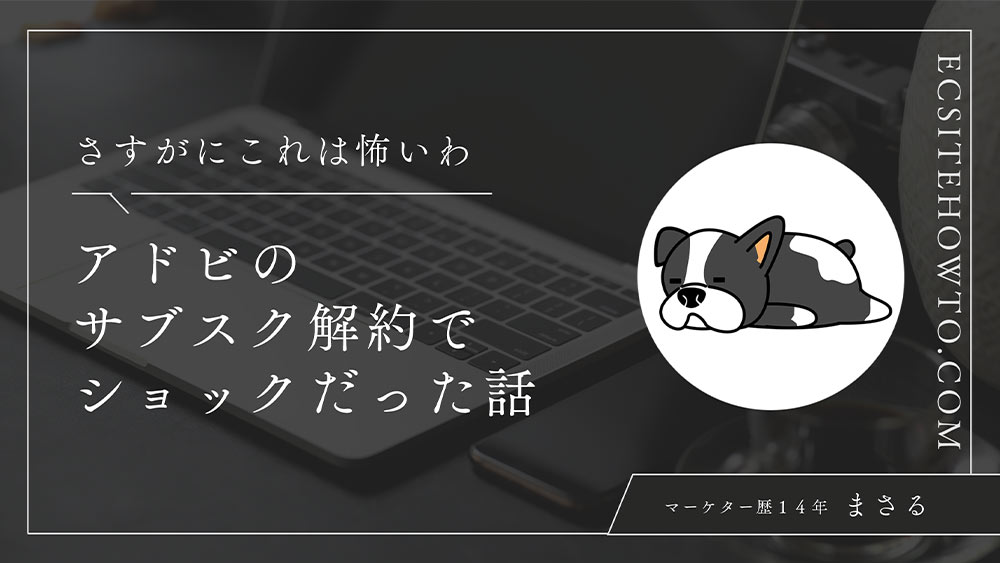
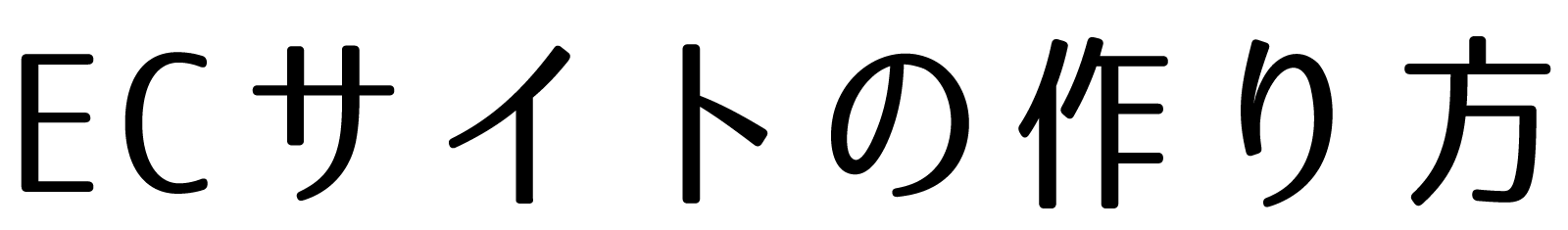




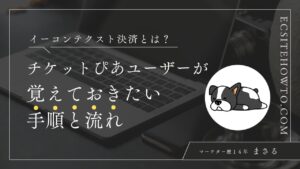


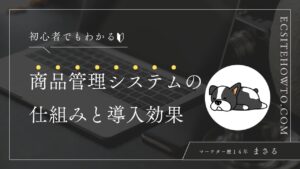

コメント