越境ECで海外販売に挑戦したいけれど、何から手をつけていいのか分からない——そんな方に向けて、この記事では「販売対応の進め方」「関税・税制の考え方」「多言語対応の実践方法」をわかりやすく紹介します。手探りで始めるのではなく、事前に知っておくべきポイントを押さえることで、失敗を防ぎ、着実に成果を出すことができます。
越境ECの基礎知識

グローバルな市場へのアクセスが身近になった今、「越境EC」は国内外を問わず注目されています。「越境EC」とは何か、そしてなぜ今それが必要とされているのかを解説します。
「越境EC」とは?
「越境EC(えっきょうイーシー)」とは、「国境を越えて商品やサービスをインターネット上で売買すること」を意味します。ECは“Electronic Commerce(電子商取引)”の略で、いわゆるネットショップのことです。つまり、越境ECは「海外の顧客にネット通販で商品を販売すること」を指します。
たとえば、日本の職人が作る和食器をアメリカの顧客に販売する、もしくは韓国のコスメブランドが日本市場に向けてオンラインで販売するという行為も越境ECです。このように、国内だけでなく、国外に向けて商品を届けられるのが越境ECの特徴です。
また、越境ECには「自社ECサイト型(Shopifyなどを活用)」と「モール型(Amazon、eBay、アリババなど)」の大きく分けて2つの展開方法があり、それぞれにメリットと課題があります。どちらを選ぶかは、扱う商品やターゲット市場によって変わります。
なぜ今、越境ECが注目されているのか
近年、国内市場の成長が頭打ちになる一方で、海外では日本製品への関心が高まり続けています。特にアジア圏では「Made in Japan」ブランドが信頼の証として評価されており、日本語が話せないユーザーでもネットを通じて簡単に購入できるようになったことが追い風となっています。
また、コロナ禍をきっかけに世界中でオンラインショッピングが加速し、消費者は国をまたいで商品を探すようになりました。実際に、2023年における日本から中国およびアメリカへの越境EC市場の成長について、経済産業省が発表した「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」によれば、以下のようなデータが報告されています。
_経済産業省.jpg)
- 中国の消費者による日本事業者からの越境EC購入額は、2兆4,301億円で、前年比7.7%増
- 米国の消費者による日本事業者からの越境EC購入額は、1兆4,798億円で、前年比13.4%増
これらの数値から、日本から中国およびアメリカへの越境EC市場が年々拡大しており、2023年には前年比で約10%以上の成長を記録していることがわかります。
さらに、ShopifyやBASEなどのサービスが登場したことで、個人や中小企業でも手軽に越境ECにチャレンジできる環境が整ってきました。かつては大企業の専売特許だった海外販売が、いまや誰でも挑戦できるフェーズに変わりつつあります。
越境ECのはじめ方とおすすめの進め方

越境ECは、専門的な知識がなくても正しい手順をふめば個人でも始めることができます。少ないリスクで始められる方法や、スムーズに進めるためのポイント、そしてプラットフォーム選びのコツまでをわかりやすく解説します。
個人・中小企業でも始められる越境EC
以前は、海外に商品を売るには代理店や現地法人が必要でしたが、いまは個人でも越境ECに挑戦できます。
越境ECは大がかりな設備投資や在庫を必要としない「無在庫型」や「予約販売型」などの方法もあります。さらに、世界中で使われている決済サービス(PayPalやStripe)や翻訳ツールを組み合わせれば、小規模でも十分に勝負できます。
本当に重要なのは、「売る商品」と「誰に届けたいか」を明確にすることです。小規模な事業者ほど、ターゲットを絞った戦略が効果を発揮します。
はじめに必要なステップと準備物
越境ECを始める際には、次のような流れを意識するとスムーズです。
準備のステップ
- 商品の選定(海外でも需要があるもの)
- 市場調査(ターゲット国の好み・競合・価格帯)
- 商品説明文の多言語化
- 通関や関税の知識の習得
- 海外配送対応(送料や梱包の確認)
- 海外向け決済方法の設定(クレジット・電子決済など)
たとえば、食品を扱う場合は「原産地表示」や「成分表の翻訳」などが求められることもあります。配送については、EMSや国際宅急便などの選択肢があり、配達日数やトラブル時の対応も比較検討が必要です。
また、税関でのトラブルを防ぐためには、輸出入のルールをあらかじめ調べておくことが重要です。経済産業省やジェトロのサイトなど、信頼性の高い情報源を活用しましょう。
越境ECに強いプラットフォームの選び方(例:Shopify、Amazon、BASEなど)
どのプラットフォームを選ぶかで、運営のしやすさが大きく変わります。それぞれの特徴を簡単に紹介します。
| プラットフォーム | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| Shopify | 世界で使われている越境EC特化型。多言語・多通貨に強い | 自分でデザイン・運営したい人 |
| Amazon(グローバル) | 圧倒的な集客力と物流サポートあり | 商品をすぐに売りたい人 |
| BASE | 日本語で操作しやすく、無料で始められる | 初心者・小規模事業者 |
たとえば、雑貨を海外のファンに売りたい個人なら、まずはBASEでスタートして、売上が伸びてきたらShopifyに移行するという方法もあります。
どのプラットフォームにも一長一短があります。重要なのは「自分の目的に合った機能があるか」「費用対効果が見合うか」をしっかり確認することです。
越境ECのビジネスモデル

越境ECを成功させるには、自分に合ったビジネスモデルを選ぶことが重要です。「自社EC型」と「モール型」、そして「直販」と「代理販売」の違いを比較しながら、それぞれの特徴や向き不向きを具体的に解説します。
自社EC型・モール型の違い
越境ECには、大きく分けて「自社EC型」と「モール型」の2つの販売方法があります。それぞれの仕組みと特徴を知ることで、自分に合った選択がしやすくなります。
| 項目 | 自社EC型(例:Shopify) | モール型(例:Amazon、eBay) |
|---|---|---|
| 集客 | 自力で行う(SNS、広告など) | モール内の集客力に依存できる |
| 初期コスト | 中程度(サイト構築費など) | 低め(出店料や手数料が中心) |
| デザイン自由度 | 高い | 制限あり |
| 顧客情報 | 取得できる | モールが管理し一部のみ取得可能 |
| ブランド力 | 自社で構築可能 | モールのブランド力を利用できる |
たとえば、日本の伝統工芸品を海外に売りたい場合、ブランド価値をしっかり伝えたいのであれば自社EC型が向いています。一方、まずは売れるか試したいという段階であれば、AmazonやShopeeなどのモール型を活用する方がハードルは低くなります。
モールで販売を始めると、レビューが集まりやすく、お客さんからの信頼も得られます。信頼が見えるようになると、自社ECに移ったときにもファンがついてきやすく、売上アップにつながります。
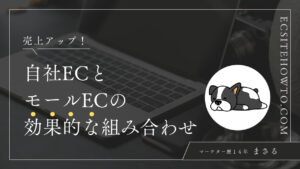
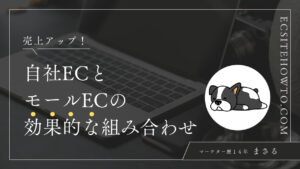
直販と代理販売のメリット・デメリット
越境ECでは、誰に向けて商品を出すかだけでなく、「どう売るか」も重要なポイントです。「直販(自分で直接販売)」と「代理販売(他社に販売を委託)」にはそれぞれ特長があります。
直販のメリット
- 顧客の反応を直接得られる
- 利益率が高い
- ブランドメッセージを正確に伝えられる
直販のデメリット
- 顧客対応や配送をすべて自分で行う必要がある
- トラブル対応の負担が大きい
代理販売のメリット
- 自分で販売・配送をしなくて済む
- 海外販路をすばやく広げられる
代理販売のデメリット
- 利益率が低くなる
- ブランドの世界観が相手に依存する
たとえば、海外の高級スーパーと契約して代理販売を行えば、現地に強いパートナーの販路を活用できるため、継続的な売上が見込めます。規模が大きくなれば、将来的に現地法人の設立も視野に入ります。一方で、雑貨やアクセサリーなどを扱う場合は、SNSを活用して直接お客さんとつながり、Instagram経由で注文を受けるといった直販スタイルも効果的です。このように、商材や目的に合わせて柔軟に販売方法を選ぶことが大切です。
どちらの方法も一長一短ですが、最初は直販でお客さんの反応を見ながら始めるのがおすすめです。慣れてきたら、代理販売なども組み合わせて広げていくと無理なく続けやすくなります。
多言語対応の基本と実践方法


海外のユーザーに商品やサービスを正しく届けるには、「言葉の壁」を越えることが欠かせません。このパートでは、英語以外の言語対応の重要性や、翻訳方法の選び方、そしてユーザーに信頼される表現づくりのコツについて具体的に解説します。
英語対応だけでいい?主要国の言語ニーズ
越境ECでは「英語対応していれば十分」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。たとえば、台湾や韓国、フランス、ドイツなどでは、英語が読めても「母語での表示」の方が購買率が高くなる傾向があります。
特にアジア圏では、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、タイ語などの需要が高く、商品説明だけでなく、カスタマーサポートやFAQも現地語対応しているショップの信頼度は明らかに高まります。
販売対象国が明確な場合は、その国で最もよく使われている言語を優先的に対応しましょう。たとえば、日本の化粧品を中国で販売するなら、英語よりも中国語(簡体字)での表示が効果的です。
翻訳ツールとプロ翻訳の使い分け
多言語対応を実現するには、「翻訳ツール」と「プロ翻訳」の2つの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、場面によって上手に使い分けることが大切です。
| 手段 | 特徴 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 自動翻訳(例:DeepL、Google翻訳) | 低コスト、即時対応が可能 | 商品名や簡単な説明文の翻訳 |
| プロ翻訳(翻訳会社やネイティブライター) | 正確で自然な表現、文化的背景にも配慮可能 | ブランド紹介、利用規約、カスタマー対応文など |
すべての文章をプロに依頼するとコストがかかりますが、すべてを自動翻訳に任せると不自然な表現になり、信頼を失うこともあります。だからこそ、「買うかどうか」に影響する部分だけは丁寧に訳すのが効果的です。
たとえば、ブランドの紹介やこだわり、返品や配送に関する説明などは、ユーザーが不安を感じやすい部分です。ここをネイティブ翻訳にすることで、「きちんと対応してくれそう」という安心感が生まれ、購入につながりやすくなります。
一方、商品名や素材名など、機械翻訳でも意味が伝わる部分はツールを活用すれば、手間や費用を抑えながら対応できます。
「すべてを完璧に訳す」より、「大事な部分を丁寧に訳す」ほうが費用対効果も高くなります。
ユーザーが安心できる翻訳表現のポイント
外国語での買い物は、多くのユーザーにとって少なからず不安がつきまといます。だからこそ、翻訳文は「自然で、信頼できる言葉」であることが重要です。
特に注意したいのは以下の3点です。
- 意味不明な機械訳を避ける(例:「とてもおいしい安心の洗剤」→「Very delicious safe detergent」)
- 現地の文化や言い回しに沿った表現を使う
- 保証・返品・配送などの情報は、丁寧かつ明確に表記する
たとえば、「30日以内なら返品可能です」は「You can return the item within 30 days.」と簡潔に表すだけでも、ユーザーの不安を大きく和らげます。
翻訳は単なる言語変換ではなく、信頼を伝える手段です。「このお店は自分の国のことをちゃんと理解してくれている」と感じてもらえる翻訳が、購入という次のアクションにつながります。
まずは主要な販売国を決め、その国のユーザー目線に立った翻訳対応を進めていきましょう。少しの気配りが、信頼という大きな結果につながります。
関税・税金・食品規制の注意点


越境ECを行う際、多くの初心者が見落としがちなのが「関税」や「輸出入の規制」です。国をまたいで商品を届けるということは、その国の法律や税制度の影響を受けるということ。知らずに販売を始めてしまうと、思わぬトラブルやクレームにつながることもあります。ここでは、最低限知っておくべき税金や規制の知識をやさしく解説します。
海外販売時にかかる関税と税金の仕組み
商品が国境を越えると、「関税(かんぜい)」や「消費税(VATなど)」が発生します。これらは、基本的に購入者が支払うものですが、ショップ側が事前に表示していないとトラブルの原因になります。
たとえばヨーロッパでは、商品価格とは別に20%前後の付加価値税(VAT)がかかることが多く、DHLやFedExで配送する際には、顧客が到着時に支払うケースもあります。日本からアメリカへ1万円の商品を送った場合でも、受け取り時に関税や手数料が発生することがあります。
対応策としては、以下の2つが有効です。
- 「関税・税金はお客様負担」とサイトに明記する
- 一部のプラットフォーム(例:Shopify)では、購入時に自動計算して表示する機能も活用可能
ユーザーに安心して買ってもらうためには、こうした「見えないコスト」もあらかじめ説明しておくことが大切です。
食品やコスメなどの規制が厳しい商品ジャンル
商品ジャンルによっては、輸出入そのものが制限されていたり、特別な表示や申請が必要なケースもあります。特に注意が必要なのは以下のジャンルです。
- 食品・飲料:成分表・賞味期限・原産地表示が求められる。国によっては成分検査が義務。
- 化粧品・スキンケア:薬用表示や効果効能の記載がNG。販売許可が必要な国もある。
- 健康食品・サプリメント:医薬品として扱われる国もあり、輸出が禁止されることも。
たとえば、日本で人気の「青汁」を海外に販売しようとした事業者が、現地で医薬品扱いとされ、通関で差し止められた例もあります。日本国内で問題ない商品でも、海外ではまったく別のルールが適用されることを忘れてはいけません。
国ごとの規制情報を調べるコツと便利サイト紹介
すべての国の規制を暗記することは不可能ですが、必要な情報を素早く確認する方法はあります。以下のような信頼性の高い情報源を活用しましょう。
- JETRO(日本貿易振興機構):国別の輸出入規制、手続き、税率などの情報が充実
https://www.jetro.go.jp/ - 経済産業省 輸出関連ページ:最新の規制や協定情報を提供
https://www.meti.go.jp/ - 各国の税関サイト(例:US Customs and Border Protection):具体的な通関条件を調べられる
https://www.cbp.gov/
また、実際に商品を送る際は、DHLやFedExのような国際配送業者のウェブサイトにも最新の通関情報が掲載されています。
トラブルを避けるためにも、「売る前に調べる」「わからない部分は専門家に聞く」姿勢が重要です。手間を惜しまず、信頼される越境ECショップを目指していきましょう。
越境ECで成果を出しているジャンルとランキング


どんなに優れた仕組みや翻訳があっても、「売れる商品」を扱っていなければ越境ECで成果を出すのは難しいものです。実際に売れている商品ジャンルのランキングと、海外ユーザーから人気を集めている日本商品の具体例を紹介しながら、取り扱う商品のヒントをお届けします。
売れている商品ジャンルTOP5
越境ECにおける売上上位ジャンルには、国を問わず共通する傾向があります。以下は、複数の調査(Shopify公式、JETRO、楽天グローバルなど)に基づいた人気ジャンルのTOP5です。
| ランキング | 商品ジャンル | 理由・特長 |
|---|---|---|
| 1位 | ファッション(アパレル・雑貨) | サイズ感・デザインの多様性。日本ブランドは品質面でも高評価 |
| 2位 | 化粧品・スキンケア | 「Made in Japan」の安心感。自然成分・敏感肌対応が人気 |
| 3位 | 健康食品・サプリメント | 長寿国・日本製への信頼が高く、美容系の機能性アイテムが特に好調 |
| 4位 | 家電・ガジェット | 小型で高性能な日本製電子機器が注目されている |
| 5位 | 伝統工芸・文具・趣味雑貨 | 和紙、箸、陶器などが「ギフト需要」として根強い人気 |
特にアジア圏では「美容」と「健康」への意識が高く、スキンケア製品やビタミン系サプリメントが継続的に売れています。また、欧米ではオタク文化の浸透とともに、日本のキャラクターグッズや漫画関連商品も堅調です。
海外ユーザーに人気の日本商品事例
「実際にどんな日本製品が売れているの?」という声にお応えして、いくつかの具体例をご紹介します。
- 資生堂のスキンケアシリーズ
欧米の消費者からは「肌がやわらかくなる」といった使用感が好評で、現地の口コミサイトでも高評価を獲得。実際、アメリカでは一部のドラッグストアで取り扱いが始まるほどの人気です。 - ユニクロのヒートテック
東南アジアや欧州でも「軽くて暖かい」と話題に。特に寒冷地に住む海外ユーザーの間でリピーターが多く、日本の機能性繊維の技術力が評価されています。 - 南部鉄器のティーポット
アメリカやフランスでは「ジャパニーズ・ティー文化」の象徴として、インテリア兼実用品として人気。見た目の美しさと重厚感が欧米の嗜好にマッチしています。 - BENTO BOX(お弁当箱)
「日本の食文化」への関心とともに、彩り豊かな弁当写真がSNSでバズり、スタイリッシュな二段重や木製ランチボックスが売れ筋に。 - 文具ブランド「ミドリ」「無印良品」
手帳や付せんなど、シンプルで洗練されたデザインが世界中のステーショナリーファンに支持され、レビュー動画やSNS投稿が販促にも直結。
越境ECで成功している企業は、単に「モノを売る」のではなく、「日本らしさ」や「安心感」をセットで伝える工夫をしています。まずはこれらの事例を参考に、自社の商品がどんな価値を提供できるのかを明確にしてみましょう。
商品選びは、越境EC成功の第一歩です。人気があるだけでなく、「海外でもニーズがあるか」「規制にひっかからないか」「発送しやすいか」などもチェックしておくと安心です。
越境ECを成功させるには、商品の魅力だけでなく、現地の言語や税制への正しい対応が欠かせません。この記事の内容を参考に、自社に合った準備と戦略で海外販売を進めていきましょう。



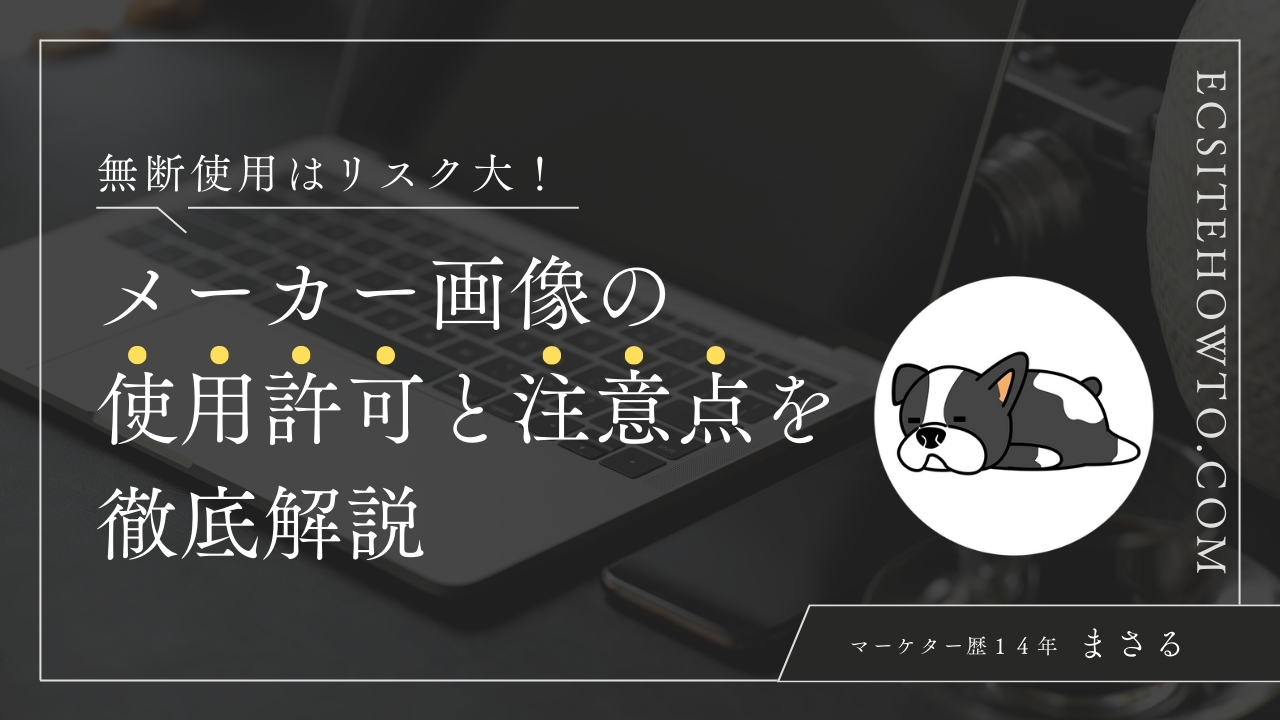

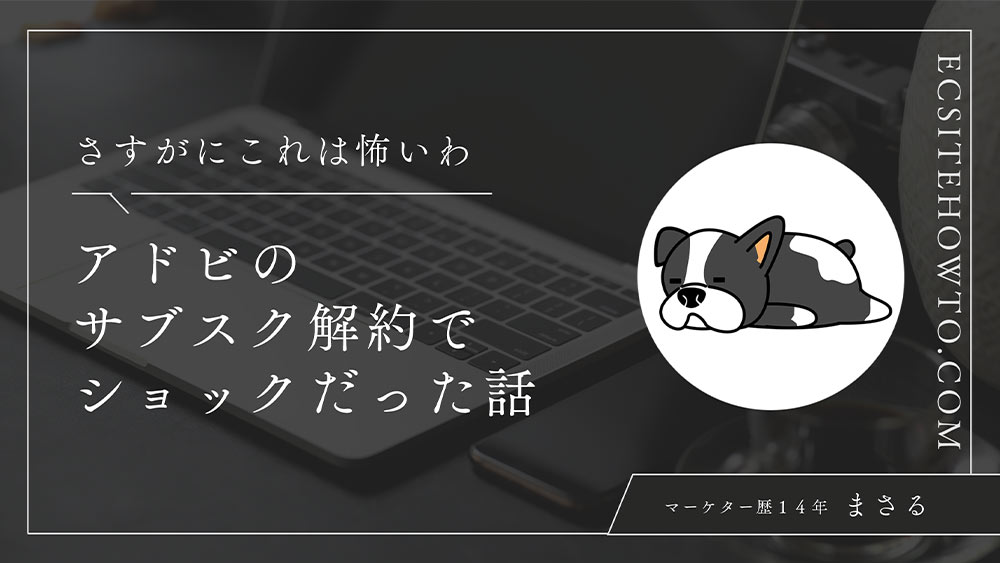
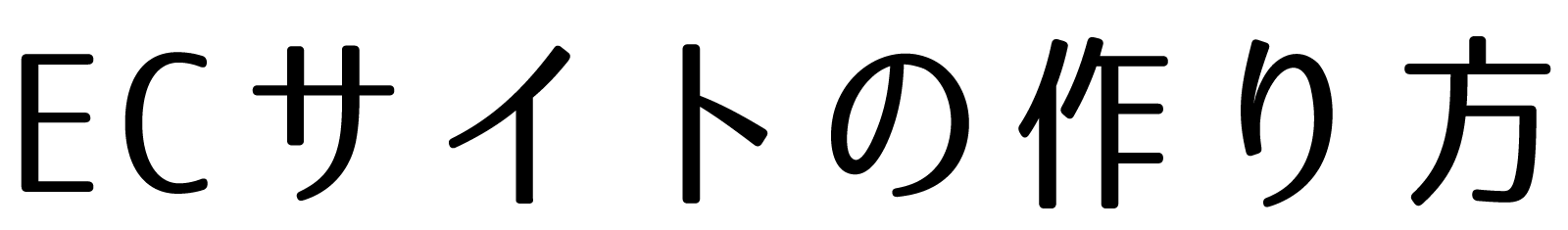
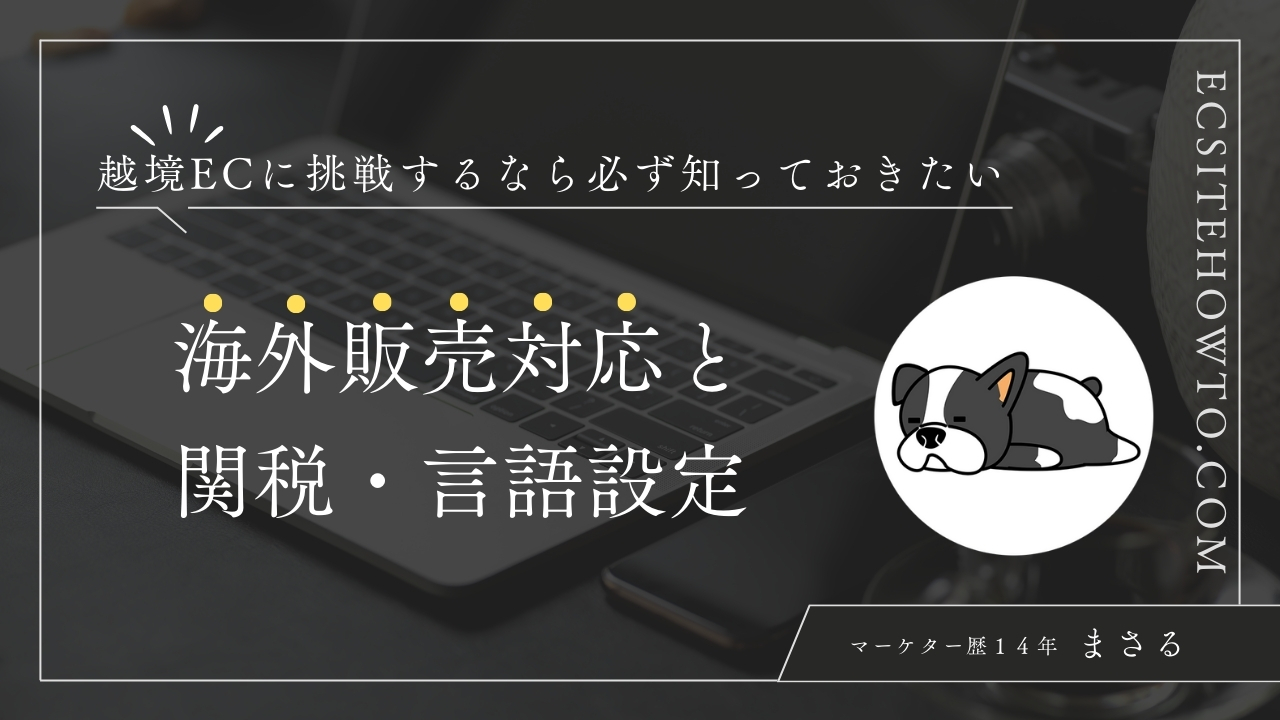



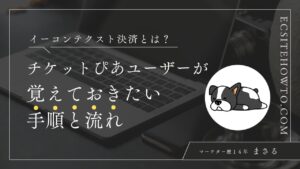


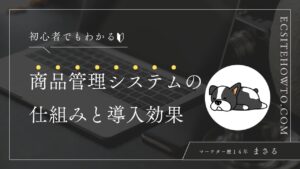

コメント